| cover | ||
 |
描きかけの油絵 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
描きかけの油絵
旅の半ばで
十一月下旬の土曜日、コトは決行された。無謀とも言えるこの計画の遂行は“衝動”でもあったが、自分の中に四十年来住み続けているあるものへの“挑戦”でもあった。 飯田を出て国道一五三号線を北上して松本へちょうど距離にして百キロメートル、一つ用事を済ませてそのあとに私が目論んでいるのは、そのまま車を走らせて京都に上ろうというも の。どの道を走らせるか、決めてない。どの宿に泊まるかもまだ決めてない。野宿とはいわないまでも、すぐ寝られるよう毛布は積んである。履物もパンプスからスニーカー、サンダル まで一そろい持った。服も運転が楽なもの、京都の街を歩いても一応恥ずかしくないもの、カセットテープは軽音楽から小朝の落語まで、と何でも気がついたものはトランクに放り込ん だ。 この三日間に私がすべきことは松本で催される『信州アルコール研究会』に出席すること、通信教育の日曜日スクーリングを受講すること、そして月曜日のお昼に飯田に帰ってくるこ と、これだけ。この三つさえ実行できればいい。 まず、飯田を出て、郊外の大型書店で千円也のロードマップを購入した。いままでは要ることもなかった全国版だが、今回はこれがなくてははじまらない。 駐車場でさっそく地図を開いて、これから自分が車を走らそうとしている道を指でたどった。自分で運転せず、人に乗せてもらって通過していた時には気にもとめなかった、高速道路 と一般道の位置関係を改めて確認する。 高速道路は使わないつもり。経験からの大まかな計算では、高速道路を利用すると一時間の時間を短縮するのに、少なくとも千円はかかることになる。乗り合わせて利用したり、時間 の制約や渋滞のことを考えなくてはならないとなると高速はそれなりの金額を払う価値もあるが、今回の私の京都行きはまったくその必要がないもので、時間は人に分けてさしあげたい ほどある。 だいたいのルートを頭に入れ、地図を閉じて真北に進路をとった。最初の目的地の松本も、よく考えてみると自分で運転して乗り入れるのは初めてで、いままで一人の時は高速バスを 利用するばかりだった。松本に来た目的の『信州アルコール研究会』、これは県内でアルコール依存症に医療や福祉の立場で関わる医師、ソーシャルワーカー、看護婦さんで構成されて いる会である。守秘義務のある職務にいる人でないと参加できないということだが、今回、女性の酒害問題がテーマで、話題提供も兼ねた体験談をという依頼を受けて出向くことになっ た。 研究会が閉会となったのは午後四時を回っていた。来た道を少しもどって、松本から塩尻に出て国道一九号に入った頃にはすっかり日が暮れていた。夜が丸ごと自分のものだ。明日の 朝、授業がはじまる九時までに教室に入っていればいい。どう使ってもいい十数時間が私の前に広がっている。夜は長い。とにかく出発だ。 断酒できている毎日がある。金曜日の例会出席はクリスチャンの日曜日の教会礼拝のように、何はさておき週間行事に組み込まれ、県外各地の研修会参加は正月、盆、クリスマスなど の避けては通れない年中行事のように恒例化して、一定のペースで繰り返されている。機関紙の『しなのアメシスト』も年八回、一ヵ月半に一度発行のペースは一応守ることができ、念 願だった地元でのアメシストの例会もなんとかスタートして、とにかく断酒の“かがり火”を点す燭台の用意はできた。県内外のアメシストの輪は着実に広がっている。 生業としての塾も、生徒の数は今の私にとって適当で、生活に融通がきく状態は保たれており、生徒とのいい関係ができていて、加えて、「私が君たちにしてやれることは大してない からね。何か手を貸すことがあれば言っておいで」という姿勢に親御さんから文句も出てない状況にあるので、そちらの方での悩みもない。 はじめたはいいが、学習の進め方もわからずに授業料を払い込むだけだった社会福祉の通信教育も、昼間の仕事を離れたお蔭でやっと腰があがり、遅々とした歩みではあるが“卒業” という一つの形に向けてとりあえず歩きだすことができている。しなのアメシストを旗揚げした頃から酒害相談を受ける機会が多くなり、その際の自分の一言の重さを痛感するようにな った私は、ある程度の援助技術を踏まえて臨む必要性を感じるようになって、生涯教育としての社会福祉を身につけたいと思って志学した。資格をとってどうのというものではないが、 社会資源を知るだけでも学ぶ意味はあると思った。 母は一昨年のヘルニアの手術から、体の不調を絶えず訴えるようになった。それでもなんとか自分のことは自分でできる小康状態を保っている。ハードなスケジュールの県外研修会な どの参加は無理だが、父と二人で連れ立って外出することぐらいは支障なく、自分の体の具合と相談しながらの一日を送ってくれている。 こうしてみると、暮らしているどの場面においてもとりあえずは平常心でいられる状況は整っているはずなのに、なぜか心に澱のようになって横たわる所在なさを私は自分で扱いかね ていた。いったいなんだろう、生活の隙間に漂うこの漠然とした不安感は。心が定まらない、そんな状態がここ二ヵ月程続いている。 南風原先生には相談した。 「すべきことはしているし、スケジュールもこなせていて、悩みの種になるようなことが身の回りにあるわけではないのに、何かこのままでいいんだろうかってことばかり考えているん です。 自分の好きなように使っていい時間や一日があっても、何かしなくちゃって絶えずソワソワしてる自分がいる。今日は時間があるから、ゆっくりテレビでも見ようか、本でも読もうか って気になれなくて。必要に迫られて何かに夢中になっている時はいいんだけど、変に時間があると不安になってしまうんです」 診察室はホントは禁煙なんだけど、と言いながら、机の下から灰皿を引っ張り出して私の話を聴いてくれてた先生。一服じゃ収まらなかった時間。 「その所在なさやぽっかりあいた時間を無理に埋めようというんじゃなくて、ゆとりや余裕って解釈して楽しむことができればいいんだけどね」 先生は、だからどうしてみましょう、ということは言ってくれない。それはいつものことだけれど、私も“いつものように”胸の内を吐露して、少し気が済んだ。 悩みともつかないことであるとは思いながらも、友人に聞いてもらうと極めて単純に「いいじゃない。別に今のままで」と言う。その通りなのだが問題は今のままでいられない、そん な状態をよしとできない自分にある。私はそんな自分にあえて拘りたいと思った。なぜなら、自分が十八歳で東京に出ていって、心に拠り所をなくしてお酒に手を出していったあの頃と 、心理状態として何か似たものがある気がしたから。 地元の高校を卒業した私は、念願の大学の学生証という身分証明付き免罪符を手にしたが、茫(ぼう)として広がる時間や東京という都会に押しつぶされそうになっていた。自分で自分 の時間をうまく使うことができない。そんな手持ち無沙汰な長い夜を持て余していた私にとって、それをお手軽に埋めてくれるお酒はなんとも都合のいいものだった。軽い気持ちで手を 出したのが、知らずのうちにのめり込んでいって、気が付いたら“アル中”のレッテルが貼られ、あともどりできないところまできてしまっていたというのがその時代である。 常に飽和状態でないと気が済まなくて、心に空間があるのが耐えられなくて、私はそれを埋める手段としてお酒を使った。バドミントンに懸けている時は、それに自分の百二十パーセ ントを出そうとする。受験勉強に取り組むようになると、睡眠時間を削ってがむしゃらに机に向かうことでしか自分の存在を確認することができないようになる。バドミントンで疲れ果 て、勉強で睡眠時間が少なくなるほどに自分が今、向上前進の途についているという手応えを実感することができ、それが快感でもあった。 ベストを尽くし、それに見合う結果を出し、それ相当の評価も得たいと思う自分がいる。それが、努力したらした分だけの結果と評価を得ていた十八歳まではよかったのだが、努力し てもそれが結果として表れない時、報われないものに遭遇した時、私はいとも簡単に挫折し、アルコールに心を逃がした。想ってもどうにもならないことがあるのが人の仲である、とい うことに遅ればせながら気がついた時もすでに手を伸ばせば届くところにお酒があり、私の堕ち方は加速度がついた。 こうしてみると、私には一つのことに懸けはじめると、自分で“いいかげん”“適当”という頃合をつかめなくなり、のめり込んでいくというパターンがあることがわかる。周囲には それが常軌を逸する状態であると映ることも、本人は半ば強迫的な思い込みにかかって「これが私の生きる道」となっている。それは、中途半端な酔いでは満足できず、一定のそして、 それ以上の酔いを求め、量がどんどんエスカレートしていき、気がついたら身体的にも薬物としてのアルコールにはまっていた、という状態にも当てはまる。 だから、頑張ってるねと周囲から評価されるまでに一つコトに夢中になっていた時も、相手との距離を測りながらの理性的な恋愛ができないことも、酒にのめり込んでいった件も、少 しも矛盾なく私の中に存在しているものであるということに、体験談を話していて気がついた。ただエネルギーを傾ける対象が何であるかだけの違いが、周囲から誉められるか蔑まれる かの人間的な評価まで及ぶ。運動、勉強と一心不乱に一つのことに打ち込んでいた頑張り屋の、その対象が酒に替わった時に手のつけようのないアル中になった。ただそれだけのことで あるかもしれない。 父は生きる屍のようになって、飲み疲れて炬燵で丸くなっている娘の頭を自分の膝に乗せて何度も何度も髪を撫でながら、幼子をあやすように、「十八歳までの倫子はどこにいっちゃ ったんだよ」と涙を流して言った。しかし、十八歳までの倫子はどこにもいっていなかった。その時の私と表裏をなすようにしてちゃんと身の内にいたのである。 県内の国立大学付属病院の神経科に入院していた時のこと、私はたしか二十七歳だった。アルコール依存症との診断を受けてからもうすでに七年目に突入しており、門を叩いた病院は その付属病院で四つ目となっていたので、大分私もアルコール依存症患者としても年季が入ってきつつあり、(続きは本書で)


 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~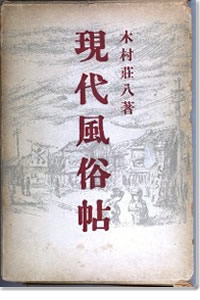 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白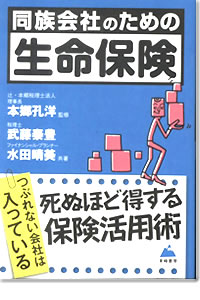 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内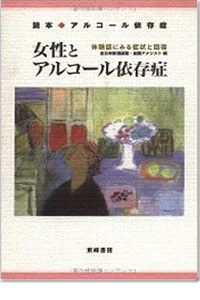 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート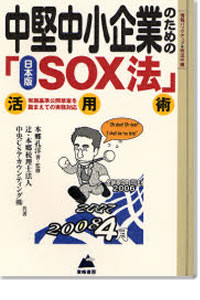 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日