| cover | ||
 |
描きかけの油絵 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
描きかけの油絵
アメシスト
〈アメシスト〉 ギリシャ神話に登場する女性です。酒の神バッカスが道で最初出会った人間をお供の虎の餌にしようと決めて道を歩いていると、ちょうどその一人と一匹の前に出くわしたのが神殿に 参拝に行く途中のアメシストでした。「どうか、私を食べないで」彼女が命乞いをして神に祈ると、彼女の体は白い石になってしまいました。哀れに思ったバッカスは手に持っていた葡 萄酒を石に注ぎました。するとその石は見る間に紫に輝く石-アメシスト-に変わりました。それに由来して紫水晶(アメシスト)には泥酔から守るという石のことばがあります。 その人との再会で私が最後まで拘(こだわ)ったのは、銀のブローチのことだった。十八歳の時にもらったもので、止め金のところが壊れて以来、ずっと私の宝石箱の隅っこに追いやら れていた。 だいぶ前になるが、今は小学校の四年生になった姪に宝石箱の整理をして、いらないものを全部やったことがある。片っぽなくしたイヤリングだとか、アクセサリーに興味を持った二 十歳前後の頃、ただ数のうちと求めたネックレスだとか、多分身につける機会はないだろうという観光地土産のブローチだとか。姪は光っていさえすれば喜んで私があてがった鏡のつい た子供用の宝石箱に、それらを次々に大事そうにしまい込んだ。私の妹は「お姉ちゃん、可愛い姪をあんまり光り物が好きな女の子にしないでよ」と言って笑っていた。 私は奥から出てきた銀のブローチを手にしてしばらく眺めた。細かな銀の細工が施してあったが、それが銀独特の錆がきているものだから、何の金属かもわからないくらいに変色して いた。少しとまどったが、「これもね」と姪の宝石箱に入れた。 やるといっても“燻し銀”の言葉も知らない姪は喜ぶ風もなく、他のものと一緒に並べていた。母の立場として子どものもらい物の点検をする妹。目ざとく銀のブローチに目をつける 。 「これ、銀じゃない。それもこんな手の込んだ……いいの?」 「うん。軽くて重宝してたんだけど、止め金のところが壊れちゃってもう使えないし、修理に出すとしても、けっこう直し賃も取られるでしょ」 「これ、たしかお姉ちゃんが前に付き合ってた人からもらったもんじゃなかったっけ。とっておいた方がいいんじゃないの……」 「……そうかなあ……そうしようか」 で、そのブローチは姪のおもちゃにならずに、またその後も私の宝石箱で生き長らえていた。 二十年ぶりに会うことになって、そのブローチのことを思い出した。宝石箱の隅から、いっそう変色の進んだそれを取り出して、ベージュのパンツスーツの下に着る黒のタンクトップ の胸元にあしらってみた。付けていっても、これだけ色が変わっていたら、あの時のものとは分ってくれないだろな……長野行き高速バスの時刻も迫っていたが、私はやおらそれを磨き にかかった。しばらくの間、ジュエリー用洗浄液に浸けておいたがいっこうにきれいにならない。仕方がない、あとは家中の洗浄効果のありそうなものを総動員させた。歯磨き、台所用 クレンザー、研磨材入りのタワシ。歯ブラシを一本ダメにして必死に磨いていると、それでもだんだんそのブローチは銀の輝きを取りもどしてきた。 キッチンの流しで格闘していると一本の電話が入った。台拭で手を拭いながら、〈この忙しい時に……〉 「もしもし」 「あのう、二週間程前の新聞で……」この声の力のなさ、女性の酒害相談である。 「新聞で拝見したんですけど、あの、出てらした方ですか?」 「はい、そうです。お電話下さって本当にありがとう」 「あの、秘密は守ってくださいますか」 「もちろんです。随分とお困りですか」 「……もう、切羽詰まってるんです」半分、涙声になっていた。 「どちらからお掛けですか。あの、私、用事があって、これから長野市に行くんです。もしよかったらお会いしませんか。飯田発八時四十五分の高速バスに乗るんですけど、お住まいは 長野市から遠いんですか?」 「いいえ、飯田まではとても行けませんけど、長野でしたら出られます」 「じゃあ、どこか私にもわかる場所を指定してくださいな」 正午、長野駅からステーションビルに連絡する改札口を出たロッテリアが待ち合わせ場所となった。 「すみませんけど、上のお名前だけでも聞かせていただけませんか」 「えっ……」 「わかりました。私、ベージュのスーツ着て、黒のバッグ持ってます。背は割りと高いから、見つけてくださいね」 「はい。私は眼鏡かけてます」 なんだか今日は思わぬ展開になりそうだ。 時計を気にしながら最後の身仕度を終えて、私はそのブローチを胸に家を出た。止め金の壊れたのはそのままだったが、針金を曲げて細工のくぼみに差し込むことでなんとか胸にくっ ついていた。 その銀のブローチの贈り主との出会いは二十六年前にも遡る。当時の私の住まいは伊那。父の商売や何やらの都合で、私は幼い頃より飯田と伊那で何度も住まいを移していた。高校時 代を過ごした伊那は、信州の南の端っこの飯田から距離にして五十キロほど伊那谷を北上する。 自分が周囲の反対を押し切ってまでして、望んで入った高校だったのに、私は入学してまもなく、とんでもないところに来てしまったと後悔した。一クラス四十七人中、女生徒は三人 。自分の居場所がみつからない。 二時間目を過ぎた頃から教室のあっちこっちで早弁が広げられて、授業がはじまっても教室にはおかずのにおいが充満している。同じ中学の出身者もクラスにはおらず、私以外の女生 徒も、皆その人なりの確固たる世界を持っている風で「ねえねえ」と擦り寄っていくこともできなかったし、もとより当時の私は相手が同性であれ異性であれそういう人懐っこさはなか った。 教室にいるうちはまだよかったが、教室移動で廊下を歩いていて、前から三年生の集団など来ようものなら、私は狭い道で大型ダンプを避ける児童のように、壁に背をぴったり付け、 息を詰めてその一軍団が通り過ぎるのを待った。 男子ばかりの教室で休み時間も手持ち無沙汰、友達もおらず、居たたまれない毎日が過ぎていった。中学校の担任の言う通り、隣の女子高校に行っておけばよかったかなあと、らしく なく弱気になった。 なんとかこの生活を変えたい、そして思い立ったのがスポーツをやることだった。ただし、その高校に入った女生徒は誰もがおとなしく勉強して、みんなそこそこの大学に進学するも のと相場が決まっていたので、女生徒が運動をやっている前例がなかった。だったら自分で開拓するしかない。中学ではバスケットをやっていたが、もちろん団体競技はできるはずもな く、とりあえず男子の中に交じっての運動部ということになると陸上か、卓球かテニス、それかバドミントン。陸上は性(しょう)に合わないし、卓球は中学の時からやっている男子にス タートの時点で差があるから、後発部隊ではついていくのが難しい。テニスは軟式でダブルスしかないので、一人ではできない。すると残されたのはバドミントンということになる。 ただし、当時のバドミントン部は数年前のインターハイ全国大会出場という栄光の余波がまだ残っていて、その栄えある時代の先輩が時々練習に顔を出してはハッパをかけているとい う部で、練習は野球部の次にキツイというのが定評だった。そんなところでやっていけるのだろうか。不安はあったが、消去法でバドミントンしか残されてないとならば迷っている暇は ない。それより何より入部させてもらえるのかどうか、許可を取り付けるのが先である。 部長さんという方を訪ねた。廊下を歩くだけでも恐いのに、三年生の教室に人を訪ねて行くなんて脅威以外の何ものでもない。三年生の教室のある棟は当時の私にしたら鬼が島か獄門 島だった。 それでもなんとか目指す教室にたどり着き、入口にたむろしている人にバドミントンの部長さんにお会いしたい、と告げた。 「おーい、女が会いたいってよ」と呼ばれ出てきた人を見て私はほっとするものがあった。何だか「この人なら」という気持ちになったことをはっきり覚えている。その場で私は一応入 部を許可された。あとで聞くと、その人は予め新入生の女の子が入部したいと頼みにくるという情報は得ていて、来たら断るつもりでいたという。ただ、まわりの悪友がおもしろいから やらせてみろ、どうせ練習についてこれないに決まってるから、と無責任な進言をしたらしい。 断じて(とむきになることもないが)一目惚れというのではない。はっきり言って私にだって理想のタイプがあった。でも教室の奥から出てきたその人と初めて会って、その時の私の 感じたものはいったい何だったろう。それは今でも説明がつかないけれど、感覚として不思議なほどよく覚えている。何だかその人の存在が胸にすとんと落ちた。 悪友の進言にまんまと乗ったはいいが、唯一その人の計算違いは、私が人並み以上の体力と負けん気があったことだった。安易に入部の許可をしてしまったことを半分後悔しながら、 しかし、もともと責任感の強い人だったから、責任上、実によく私の面倒をみてくれた。 ある時、言いにくそうに話を切り出された。 「あのさあ、池田も一所懸命練習についてこようっていう気持ちはわかるけど……」保健の先生に相談して、女子の体力からして男子のどれくらいの練習量にとどめておくのがいいかな どのアドバイスをもらったらしく、私にみんなの六十パーセントの練習量にしておくようにと言う。たとえば、みんなが五十回の腕立て伏せをするなら池田は三十回でいいから、と。だ けど私は耳を貸さなかった。どうしてもできないものは諦めるけど、ついていけるものならついて行きたい。足をひっぱらないようにするから、みんなと一緒にやらせて欲しいと頼んだ 。しょうがないなあという表情をしながらも、ロードワークのランニングはみんなから遅れた私の横を走ってくれた。 その人への思いとして近い言葉は“慕う”だったかもしれない。“慕う”気持ちが通じてなんとなく“つきあう”ようになった。最初は後輩の思いに応えてあげようというものだった ようである。それでもそれは、部の面倒見のいい先輩と放っておけない後輩の女の子という枠をそんなに出ないもので、一緒に帰るのでもなくもちろん手をつなぐでもない。今日々の高 校生に言ったら「おばさん~、そういうのは~“つきあう”って言わないの~」と語尾を上げて笑われそうだ。 ただ、私にとってその人はたしかに大きな存在だった。たくさんの影響を受けた。自分の考えというものはなかなか持てない私だったが、それより前にいつも「あの人だったら、どう するだろうか」「どう考えるかな」とその人を窓にして世間の物事や事象をみる癖がついていった。そしてその人は私にいろんな初めての体験をさせてくれた。 高校一年の時、初めて喫茶店に連れていってくれたのもその人。地下にあるそこは想像していたより暗くて、何だか自分が居てはいけない場所のような気がした。 私に初めて長い長い手紙をくれたのは彼が都会の大学生で、私はまだ田舎の高校生の時だった。二十歳の誕生日の前日に書かれたものが最長で、航空便箋十数枚が几帳面な字で隙間も ないほど埋まっていた。明日は東京の雑踏を一人で、ただあてもなく歩くんだとあった。そして長い手紙のあとには必ず、こうあった。《この手紙を読んだら早速にも勉強に取り掛かる こと。この手紙は誤字脱字、文脈の乱れなどをチェックしながら現代国語の勉強のつもりで読んでください。返事はいらないといいたいが、やっぱり欲しい。ただし時間がもったいない から、君は僕が時間に飽かせて書いたこんなだらだらした手紙に付き合って長い返事を書いていてはいけない。短いものでいい。ただ、大事なことは何かよく考えて、要点のみ書くこと 》 ある時の手紙にこんなことが書いてあった。《いままで随分、君に宛てて手紙を書いたが、まとめると本になるかもしれない。タイトルは『冷たい女の子と付き合う法』なんかがいい ですな。それに僕が有名になったら、この手紙は価値が出るから、とっておくといい》冷たくしているつもりはないんだけれど、私はつきあっている期間が長くなっても、最初のその人 との向き合い方を変えることができなかった。 その手紙は暗記するほどに何度も何度も読み返して、しばらくは私の宝物だったが、さすがに結婚する時に焼いた。その人も、今それを聞いてほっとしていることと思う。 その人が大学二年、私も遅い受験勉強のスタートを切って、なんとか勉強の進め方が分ってきた高校三年の秋だった。駅前の喫茶店で待ち合わせした。そのころから私は、その人と喫 茶店に入るときはクリームソーダを注文するのが常だった。理由は会話が途切れた時、グラスの中のクリームを突っついて遊ぶことで、なんとか時間を埋めるため。気まずいというほど の空気ではなかったが、私にはその無言の時間を楽しむ余裕はなかった。 ずっとあとになって、「天使が飛んでいる時間」とかいう形容を耳にするが、それとも違うような気がする。「天使が飛んで行く場所がわからなくて困ってうろうろしている時間」と でも言おうか。 コーヒーは高いお金を出してまで飲むものではないと思っていた。その味もわからないほど私は子どもだったし、大好きなチョコレートパフェも頼みたかったが、食べるのに一所懸命 になってしまうのが恥ずかしかった。それに時間を置いたらその正体がなくなってしまうのも格好悪い、というところでのクリームソーダだった。 会話といっても私が話すことといったら、受験勉強の進み具合ぐらいのものだったろう。自分が何を話したかほとんど覚えていない。実際、私が今のように「私はこう思う」と必要以 上に主張するようになったのはずっとあと。当時の私は無口というのではないけれど、自分の考えをはっきり筋道たてて人に伝えるということはできない女の子だった。その人からでな くとも「あなたはどう考えるの」とか「どう思うの」という鉾先(ほこさき)を向けられるのが本当に苦手だった。考えたり思ったりしなかったわけでもなかったろうが、それを伝達する 手段に事欠いていた。 その人が東京の学生生活のことをぽつりぽつりと話す。学生運動も下火になってはいたが、その燃え残りの分子が燻(くすぶ)っている時代だった。独特の字体の檄文が立看板に書き殴 られてキャンパスのあちらこちらに置かれ、時折マイクでアジを飛ばしている学生も見受けられたが、ほとんどの学生は長い髪をして、裾の広がったベルボトムと呼ばれるジーパンをは いて、その脇を関係ないねといった風で通り過ぎていた。これ以上ないノンポリ学生だった私は、彼の「東京キャンパス便り」の中に出てくる“セクト”ということばの意味がわからず 四苦八苦していた。知らないことより、知らないことをそのままにしておくことがもっと恥ずかしいことであるということに気づいたのはそれからもっとあと。その時は、会話のキーワ ードになっている“セクト”を「どういう意味?」と素直に尋ねることができなかった。一所懸命、一言一句、聞き漏らすまいという努力はしていたけれど、窮屈な精一杯の背伸びもし ていた。 会話が途切れて、私は浮かんだアイスクリームをかきまぜて、緑の液体に溶け込ませようとしていた。陣取ったいつもの場所から見える駅へ向かう人の流れにぼんやりと目をやりなが ら、その人は言った。 「俺のこと、どう思ってる?」言い終わった時はしっかり私の目を見ていた。どきっとして、私はあわててまたクリームソーダの作業をはじめて、必死に返事の言葉をさがした。 だいぶ時間をかけて、やっと見つけたのが、 「……いてもらわなくっちゃ、困るって感じかなあ……」 「ふうん……」 「いけない?」 「いや、そんなことない。けど、俺は単純に好きだよ」私は手を休めることなく、それでも上目使いで様子を伺った時、少しその人の表情が険しかったような気がした。 どうしても「好き」とは言えなかった。「私も」とも言えなかった。彼の「けど」から、そう言ってしまえば相手は少なくとも満足してくれる、微笑んでくれるとは分ってはいたが、 言ってしまうとそれは自分に嘘をつくような気もしたし…… その人は、私が大学に合格して東京に出ていったら、まず野球の早慶戦に(その人は慶早戦という)連れていくんだと言っていた。だから絶対に大学、落ちないでくれよ、と。 私はその人の言いつけを守ったわけではないが、最後のスパートが効いたのか、なんとか浪人は免れて大学にひっかかった。ただし、彼とは早慶戦を違うスタンドで応援しなければな らない身の上になってしまって、その人の念願はついに果たされずに終わった。 大学一年の時、初めてお酒を飲みに連れて行ってくれた。原宿にあるパブで、その人は新しいボトルを入れた。自分の名字を使わず、名字の一文字を使った別の氏をこしらえて銀色の ペンで手慣れた様子で角ビンに書き込む仕草がずいぶん大人に見えた。「こういう場所ではこうするもんだ」と私に指南してくれているようだった。 高校三年の時の卒業式のあとのクラスの解散コンパで、ひどい二日酔いにたたられる飲み方をした私は、大学に入って飲み会があっても、決して自分の意思で酒は飲みたいとは思わず 、懸命に食べて会費の元をとろうとする口だった。だからそれ以来のお酒ということになる。 その初めて飲みに連れていってくれた先で、私はしこたま酔っ払った。初めての雰囲気のところで、初めて男の人と二人っきりで飲むなんて、量もペースも分からない。化粧室で自分 の姿を写したら、真っすぐ立っているつもりが右へ左へ大きく揺れているのがわかった。ふわふわして宙を浮いているみたいないい気分だった。泣いたような覚えもある。そしてブラッ クアウトにはならなかったが、その後ひたすら眠くなった。帰りの電車の中でも私はちゃんと座っていられないほど、ただただ眠かった。私の顔を心配そうにのぞき込んで言った。 「俺のこと信用してくれる?」 「します。します。ずっとしてます」 「じゃあ、俺のアパートに連れていくからな」 私とその人の最寄り駅は、西武新宿線で二駅しか離れていない。 妹さんと二人暮しで2DK、私の四畳半とは随分違う。ちょうどというか、あいにくというか、運よくというか、妹さんは帰省していて留守だった。 居間兼その人の部屋の真ん中に布団をひいてくれ、私はそれも待てないくらいに服を着たまま布団に倒れこんだ。それほど眠かった。 どれくらいたったか、ふと人の気配がする。薄目を開けると私の枕元にその人が座っているようだ。とはいうもののその時の私は、危険を感じるとも期待するともなく、「あっ、いる な」と確認しただけでまたすぐ睡魔に引き込まれた。ただ、時間の経過は定かでないが、襖がコトリと音をたてたのを意識の遠くで聞いた気がする。 朝、目が覚める。と、同時くらいにその人が妹さんの部屋から出てきた。 「送っていくよ」 アパートを出ると霧が立ちこめていて、駅までの道程、電車の中、私の下宿まで、やっぱりその人の口数は少なかった。 私は酔って男の人のところに泊るという初めての、とんでもないことをしたわけなのだが、親戚のお兄ちゃんの家に泊めてもらったみたいなところで「イケナイ」ことをしてしまった という意識はなかった。しばらくあとになって、あの時、私の枕元に座っていたみたいだけど、何を考えてたのと聞いたことがあった。 「いや、いくらなんでも、酔って男の部屋に泊まるっていうのは一般常識として、俺も何かしなくちゃいけないのかな、するべきかなあって思って……一応考えてたんだ」どこまでも真 面目な人なのだ。そんなこと、しなくちゃいけないとか、するべきかなんていうレベルの話だろうか、とは今になって思うことである。 私に初めて香水をプレゼントしてくれた。彼が大学三年、ゼミで東南アジアに研修旅行に行ったお土産に件の銀のブローチと一緒に買ってきてくれたものだった。ディオールのディオ リッシモ。それ以来、私はくちなしの花が好きになった。香水の本を買って勉強した。 お土産話のついでのようにぼそっと言った。「世間では、男が東南アジアへ旅行に行くということになれば、その、行った先でやってくることは相場が決まっているんだ。俗に言う、 女の人を買うっていう……で、池田は俺がそういうことして来たと思う?」私は間髪入れず、「そんなことするはずないじゃない」私としては何を言い出すのというところ。彼はオーバ ーなくらい肩をがっくり落として言った。「みんなそう言うんだ……」 今なら、「で、本当のところは?」と真相の究明にかかるところであろうが、当時の私はそんな言葉の用意もないほど「そんなこと、絶対にするはずのない人」と思っていた。 帰省した先の田舎で会った。お父さんの車でのドライブ、何だかいつもよりニコニコしている。しばらくすると「これ見て」といかにも自慢気に走行距離のメーターを指差した。まさ にその時、数字が五万キロに変わろうとしていた。聞けば、今日のこの日にこの感激を味わおうと、昨日は一人でだいぶ無駄なドライブをしたらしい。 今、そんなことしてくれる人がいたなら、首に抱きついてこれ以上ない感激をボディランゲージで表すぐらいのことはできるかもしれない私だが、その時はどうリアクションしたか覚 えていない。当時の私を思い返すと多分、乾いた笑いを見せたような気もするし、もしかしたらその人の労をねぎらうどころか、そんな子どもっぽいことで喜んでと生意気にたしなめた かもしれない。 深緑の中のドライブ。天竜川沿いの悪路を走って車は停まる。私はまずいぞと思う。なんだかどこかで見た三文メロドラマの舞台が整いつつあるようだ。彼は台本通り運ぼうとしてい る。私は筋書きを書き換えようと必死になって、助手席の窓枠にしがみついて外の景色を凝視していた。 「おかしいなあ、こういう雰囲気づくりをすればいいって聞いたのになあ」とぼやいていたのが妙にくすぐったくておかしかった。 教室を訪ねて初めて会って、十五歳でその人の存在がすとんと私の胸に落ちてから、大学生になってもその人は同じ形で私の中で住み続けた。変わらなかった。ただ彼は変わりたいと 思っていたようである。私だって、清く正しくなんて思ってたわけではないのだろうが、なんとなくその人とは似合わないような気がしてならなかった。 大学に入って、私はバドミントンの同好会に入った。そして半年経った頃、体育会に移った。やっぱり勝つことを目的としてしかラケットを握ったことのない私にとって、同好会の雰 囲気は馴染めなかった。大所帯の中には練習よりそのあと、喫茶店でダベることが楽しくて集う人もいて当たり前なのだが、どうしてもそういう人たちと一線を画したいと思う頑な自分 がいた。体育会に入部して、私の一日はまた高校の時のような生活になる。女子大生が華やいだ雰囲気をつくっているキャンパスをジャージ姿で走り回る。授業と練習を両立させること はそんなに簡単ではなかった。 そんな私をその人は遠回しにたしなめた。バドミントンもいいが、大学生である今しかできないことがあるはずじゃないかと言う。私にもっといろんな世界を見るべきだと言う。そし て自分の同級生の話をして、こうやって学生のうちから見識を広げている人もいるんだぞと言った。その人は彼の会話の中に時々出てくる女の人だった。茶道に深くかかわっていて、そ の関係で彼女は今度、ハワイにもいくんだという。その時、私はちょっと胸がチクッとした。彼はもちろん教育的な見地から、私にハッパをかけるつもりで言ってくれているのだろうが 、ちょっとひねくれて〈どうせ私はしがない煎餅屋の娘だもん。あなたの学校での交友関係の人たちと比べてもらったって困る〉と胸の中で呟いた。ただその時は、私は時間の使い方が 分からないから、バドミントンしかできないというようなことを言った覚えがある。すると「そんなに時間があるんだったら、俺に声をかけてくれればいいじゃないか」と納得いかない というようにその人は言った。 私が大学生になったら、一緒にキャンパスライフを楽しもうと思ってずっと待っていてくれたのに、私は自分の世界に入り込もうとしていた。俗に言う大学生の普通のカップルになり たがらない私だった。 私の中のその人の存在が少しも変わらないというのは、自分の中では筋が通ったことのような気がしていたが、考えてみれば人も成長し時代も環境も価値観も変わっていく中で、人間 関係が変わらないことの方が不自然なことではある。しかしそれは今にして言えることで、当時の私はその人の困惑を慮ることができなかった。その人の中の私が次第に変わっていって 当り前なのに、私はそれに気づこうとしなかった。 同好会が嫌で体育会に入った。しかしそこで私を待っていたのは「勝てない」という初めて味わう挫折感。高校で少しばかり強くて、全国大会に出たくらいでは通用しない。それまで の私は、世の中、大概のことは頑張ればなんとかなるものだと思っていた。努力は必ず報われるものであると信じて疑わず、それなりの手応えをいつも感じることができていた。 しかし私はこのとき、頑張ってもどうにもならないことがあるということを初めて知る。努力が報われないこともあると。随分遅い“気づき”である。午後のほとんどを練習に費やし 、休みの日は遠征に行く。なのに毎日勝てなくて悔しく情けない思いばっかりだ。 せっかくあんな思いまでして大学に入って、私はなんでこんな苦しい毎日を過ごさなくてはならないんだろう。自分以外の学生がみんな青春を謳歌しているように見える。でも、もう 一度、バトミントンに真剣に取り組みたいと同好会から体育会に移ったのに、試合に勝てないのが辛いからやめたいなんて意地でも言えない。それまでに味わったことのない辛い毎日だ った。 そんな状況から「逃げたい」と思っていた私を助けてくれる事件が起こった。郷里で両親と妹、家族三人の乗った自家用車が、飲酒運転の車と正面衝突するという大事故に巻き込まれ たのである。 夜中、消防署からの電話を大家さんが取り次いでくれた。翌朝、私は交通機関が動き出すのを待って、取るものもとりあえず三人が重軽傷で収容されている病院に駆け付けた。病室に 一歩足を踏み込むと、ミイラのように包帯をぐるぐる巻きにされた母が目に飛び込んできた。「倫子、お母ちゃん、こんなになっちゃったよ」と半泣きの母。稼業の煎餅を焼く機械が再 び動きだしたのはそれから半年も過ぎてからだった。こちらに非はなくとも相手が任意保険に入っていないことで問題はこじれた。私は休みのたびに帰省して病院へ通った。たしかに初 めの頃は、なんとか家族がまた普通の暮らしができるように、私が心の面だけでも支えたいと思って田舎にその都度帰っていたのだが、それが次第に、これで体育会のバドミントンをや めるいい大義名分ができたと思うようになった。逃げる口実を見つけたような気がした。時期もちょうど年度末、二年生から新しい学生生活を送ることができる……多分、その時私は、 それまでの人生で初めて辛いことから逃げた。 母の事故の後遺症はその後も尾を引いたが、なんとかなって、私は知人の紹介してくれたケーキ屋さんのアルバイトに精を出した。そのうち離れた体育会のバドミントンの先輩で、な んとなく憧れの人ができた。でもその人は当時流行った太田裕美の『木綿のハンカチーフ』をよく口ずさんでいて、その歌詞通りの恋人が仙台にいるらしい。その人がカティサークの君 である。 帰省して母に「好きな人ができたんだ。片思いなんだけど、バドミントンの先輩で、仙台の人で」と報告した。母は付き合っているはずの人のことをいう。 「あの人は、そういうのとは違うんだよ」何が違うかまでは説明できなかった。 ちょうどその頃、その人に話があるからと渋谷に呼び出された。電話の声からして、デートどころか、今日は楽しい話ができるとは思ってきたわけではなかったが、断る理由も見つか らなかったので、いつものようになんとなく出向いた。 私が約束より早い時間に行ったのに、その人はもう来ていた。席についてたしか、その時も私が頼んだのはクリームソーダだっただろうか。 彼はやおら、レポート用紙を取り出した。そして、今日はきちんとした話をするつもりだという。いったい何がはじまるんだろう。 レポート用紙には質問事項がいくつか書いてあって、私の答えによって次の質問に移るという形式になっていた。昨夜、睡眠時間を削って作ったんだと真顔で言う。 「まず……」「じゃあ……」「て、いうことは……」いろいろ難しいことを言われてもうまく説明できない。要するに彼は私の気持ちがわからないという。私が高校生のうちは大学の仲 間に、お前のは中学生のガキの恋愛だって馬鹿にされながらも、それでもいいと思ってきた。ただ大学に入ったらそれなりの付き合いをしようと思っていたのに、この段になって私の心 ここにあらずのようで、誘ったら出てくるのにそれが楽しそうでもないと言う。 「俺のこと、いったいどう思ってるんだ」高校の時と同じ質問をされた。けれどあの時とは違い、語気が荒かった。そして私はやっぱりあの時と同じくらいの時間をかけて言葉を探して いた。 「私の心には部屋が二つあるんだ」 「……」 「一つは分譲で一つは賃貸。分譲の方は会った時からあなたに売り渡してあって、これまでもこれからも、ずっと先もその部屋の住人は決まってて、他の人が住むことはないと思う。で 、もう一つは賃貸だから住む人が変わって出たり入ったりしてる。でね、私はこっちが恋愛の部屋じゃないかって思うんだ。ドキドキしたり、ときめきがあったりっていう」 「俺はそんな器用な部屋の住人の住み分けなんかできないよ」 「……」 「待ってたら、俺はもう片っぽの部屋の鍵ももらえるのか?」 「……無理だと思う」 私は残酷なくらい正直だった。 「じゃあ、俺は池田にとって、父兄か。保護者みたいなもんなのか?」 「そんなんじゃないけど……」けどのあとの言葉が続かない。 長い沈黙があった。天使は飛ぶことを諦めているようだった。 そんなこと言ってしまって、もう私のことなんか呆れて誘ってなんかくれないだろうと思ってたのに、また電話があった。夜の八時までなら大家さんが取り次いでくれる。会おうとい う。また気まずくなるのいやだなあと思いながらも出ていく。会ったなり開口一番、 「来ないかと思った。さて、どうする?」 「お酒が飲みたい」私はそう、はっきり言った。 私はその時はまだ、自分で自分のためにお酒を飲むことは覚えておらず、一人酒をすることはなかったが、お酒を人との付き合いの潤滑油としてこんないいものはないとは思うように なっていて、女友達と酒を酌み交わすことは時々あった。だからその人との気まずさをお酒でなんとかしたいということで、その言葉はごく自然に口をついて出た。 季節は秋も深くなりかけていた。彼はもう就職先が地元の新聞社に決まっていた。今よりもっとマスコミがもてはやされていた頃だったと思う。百名以上の受験があって、最終的に採 用されたのが二人だと言っていた。私はおめでとうと言ったかどうか。へえ、すごいんだと言ったか言わなかったか。 あれは夏も盛りのことだった。田舎の公園で自分の就職が決まったら、旅行に行ってほしいと言われたことを思い出す。清く正しいお付き合いの私たちがそんなことをしていいはずが ない。でもちょっといたずら心が働いた。じゃあこれで決めよう。そう言って私は近くに生えていた通称ひっぱり草・オオバコを摘んでその人に手渡した。あなたが勝ったら行ってもい いよ。私が勝ったら行かない。負けたってなんとか煙に巻いて行かない算段はいくらでもできると思った。引っ張りっこの勝負の結果は何度やっても私が勝った。私は嘘をつかずに済ん だのに、手応えがないようでなんとなくつまらなかった。 その人の部屋で飲むことになり、二度目の訪問。妹さんはまたいなかった。その人は押し入れから、リザーブとオールドを出してどっちがいいかと差し出した。私は可愛い子ぶって、 甘い方がいいなと言う。ウイスキーで甘いもないもんだ。その人は「このテの酒を飲む学生は一応ブルジョアということになっている」なんて言いながら栓を切る。 最初に来た時はかなり酔っ払っていたし、次の朝も「おはよう」の挨拶もそこそこにお暇(いとま)してきたものだから、どういう部屋だったかという記憶はあまりなかった。で、改め て部屋の中を見回した。一つ発見したのがやなせたかしのパネルだった。高校生の私がその人に贈ったもの。なんだか乙女チックで気恥ずかしかったが、そこに書いてある詩は切なくて 、諳(そら)んじることができるくらい今でも好きだ。 --空を見上げていたら、星が流れた。ぼくはその星をいっしょうけんめい追いかけた。一晩かかって落ちた場所にたどりついたら、朝そこにあったのはただの石ころだった。昨夜はあ んなにキラキラ輝いていたのにね-- たしか、そんな内容の詩だったと思う。 会話が続かないものだから、飲むのに懸命になる。 「ひざ枕をしてくれ」急に言う。びっくりした。いやだよそんなと断った。けれど、そんなその人をいままでに知らないくらい、強引に私の膝に頭を乗せてきた。お酒の力を借りてのこ とは分った。私は言わなくてもいいことを言った。 「私、好きな人がいるんだよ。そんな私のひざでもいいの?」 「……それでもいい……」 目をつぶって、腕を組んで背を向けて何も話さず、それでも私のひざ枕で横になっている背中が少し丸まっているのがなんだかすごく悲しくて、でも私はかける言葉もみつからなくて ずっとそのままだった。 春になった。私は三年に進級して、その人も、勝手に憧れていた人も社会人になって出身県にもどり、東京からいなくなった。 私に素晴らしい恋人ができた。それはお酒。こんなに心を許した相手はいないほど急接近した。飲み残しのカティサークを初めてひとりで飲んでから、私の生活がお酒中心に回ってい くようになるまでそう時間はかからなかった。 私は今でも、大学三年の時自分がどうしていたか思い出せない。当時履修していた科目はほとんどが優だったから、おそらく授業だけは真面目に行っていたのだろうが、体育会はやめ ていたし、サークル活動をしていたわけではないし、勉学に勤しんだ記憶もアルバイトに精を出した記録も友人と学生生活をエンジョイした思い出もない。だからかなりの時間、お酒が 時間を埋めていたのだろうと思う。 ぼんやりとなんとなくの学生生活が過ぎていった。ただお酒の量は確実に増えていった。 七月だっただろうか。一通の手紙が舞い込んだ。差出しは長野のあの人からだった。それまでその人からといえば、菓子箱に収まらないくらいの手紙をもらってきたはずだったのに、 そのたった便箋一枚半の手紙に私の心は捕えられた。 以前のものと差出人が同じ人物かと疑いたくなるくらいの筆跡と文面。癖のある「ら」の字は変わらなかったけれど、乱暴なほどに熟れた「書く」ことを生業とした職業人の字になっ ていた。それまでもらったものは、そのまま国語の教科書に載せてもいいような、親にだって見せられる文章の運びだったのに、その時私に宛てられたものはなんだか自分をちょっと卑 下してみたり、世を拗(す)ねたみたいなところがあって、そのやくざっぽさがなんともかっこよかった。とどめは「強引にでも君を自分のものにしておけばよかったかもしれない」その 言葉に私は射抜かれた。 九月に入った夏休みに友達と能登半島を回る貧乏旅行を計画、夜行列車とユースホステルを使って、足掛け八日の旅の最後は連れと別行動をとり、私はその人を訪ねるために長野に途 中下車する日程を組んだ。 その頃は、毎晩四畳半の学生アパートで一人でお酒を飲むのが習慣になっていた私だったが、宿泊がユースホステルということでお酒はご法度だったし、一泊だけの贅沢、民宿の夕食 に私がいける口であることを知っている一緒に行った女友達が「ビールでも頼んだら」と勧めてくれたが、まだ私は体裁をつくろうくらいの理性があって、旅行中はずっと飲まなくて済 んでいた。 金沢で友達と別れて、北陸本線、信越本線と乗り継いで長野に入る。時間だけはたっぷりある学生の周遊券旅行、しばらく駅で待つことになる。 その人は、仕事からとりあえず解放されるのが夜の十時過ぎということで待ち合わせた時間は夜も更けてからとなった。出会って以来、曲りなりにも“つきあって”きた中でこんなに 会うことに胸をときめかしたことはなかった。あの手紙を書いた人はどんな社会人になっているのだろう。 「悪い、悪い」と言いながら、約束の時間より少し遅れて登場した。これからどうしようとも聞かずに、当り前のように車を真っすぐ自分の家に走らせた。暗いからよくわからないが、 築からだいぶ経っている一軒家を借りているみたいだった。本当に寝に帰るためだけの家のようで、玄関ともいえない入口にさっそく、新聞だか新聞紙だか区別がつかない商売道具がう ず高く積まれている。それを蹴飛ばし、隅に寄せて座る場所を確保していた。変わったなと思う。以前なら、私が来ることがわかっていたら、きっと掃除をするなりして迎えてくれただ ろうに。そんな素っ気なさがいいなと思いながらも本当に私、歓迎されているのだろうかと少し不安になった。 臆面もなく私は、途中の車の中で部屋にお酒があるかどうか聞いた。付き合いで酒は飲むが、元来の酒好きでもないその人は、家でお酒を飲む習慣はないようで、そんなものは置いて ないという。私は飲ませてほしいと言った。まったくもう、酒飲みは困ったもんだなどと言いながら車を停めて、自動販売機でワンカップを二、三本求めた。 記者稼業を「ヤクザな商売」と言ってみたり、会話の端の「サツ回り」とか「他社に抜かれた」とかが新鮮だった。私のことを丁寧に扱ってくれないことも。 東京にもどってから私は旅行先で撮った写真と一緒に手紙を出した。 その人からはまた遊びに来てくださいという短い返事があった。 少しずつだけど確実に、お酒の量が増えていっている不安感を除けばいい夏だったと私は思った。 再び長野に出向いたのはその年の十一月。同じ時刻に駅で待ち合わせる。少し離れた駐車場に車を停めて降りた時に見上げた夜空、満天の星、私はその星の数の多さに目を見張った。 長野の市街地で降ってくるほどのこんな星空が見られるなんて。二十年経つけれど、あれほどの星をいっぺんに見たことはまだない。 部屋に入ると、せっかく買ったのに飲まなかったこの前のお酒がそのままになっていた。 次の朝、うまいもんを食おうと午前中の胃にはヘビーなお店に入る。交わす言葉は少なかったけれど、無言の時もあったけれど、私は前のようにそれをしんどいとは思わなかった。そ の時はそこに天使が飛んでいると思っていた。だけどそう思っていたのは私だけだった。 突然彼が言い出した。 「もう、会わないようにしよう」 「えっ?」 「会わないようにしよう」 「そんな……どうして?」 「会っても、しょうがないから」 しょうがないってどういうことなんだろう。頭の中が真っ白になる。 しばらく何も考えられない時間。真っ白が水色になってそこから見る間に涙が溢れてきた。 「どうしてそんなこと急に言うの。理由を言ってほしい……」私が涙でぐすぐすになりながら尋ねてもそれ以上は何も言ってくれず、その人は黙々と食事を続けた。だって遊びにおいで って言ってくれたから来たのに。その私を昨日、それも昨夜迎えてくれて、それから十二時間も経ってないのにどうしてそんなことが言えるのだろう。私は昨夜からこれまでの時間の中 でその人にそんなことを言わせるようなことをしたのだろうか。 何で、どうしてが頭の中でぐるぐる渦を巻いた。涙があとからあとから流れてくる。嗚咽(おえつ)を奥歯で噛み堪えているものだから、耳の奥が痛くなった。どのくらい時間が経った かわからない。 「〇時△△分の上りの列車がいいと思う。駅まで送っていくよ」と私を促し、レシートを持って先に立って行った。 何だか悪い夢をみているようだった。何なんだろうこれは。現実? 気が付くと信越本線上りの急行列車の中にいた。列車の窓の外は雨だったような気がする。はっきりと覚えているのは、額をくっつけて泣いている窓が曇っていたことだ。長野を出た 時、ボックス席は私一人だったのに、途中から人が大勢乗り入れてきて、隣も斜め前も席が埋まってしまった。恥ずかしかったけど、そんなこと気にしてられなかった。堪えたって、勝 手に涙が出てくるのだ。それに、もうあの人を訪ねていくことがなければ、この列車に二度と乗ることはあるまい。旅の恥はかき捨てだ。そう思うと余計に涙が出た。この年になってこ れほど泣ける涙の埋蔵量があることに驚いたけれど、そのうちに頭の芯が痺れてきて、何で自分が泣いているのかもわからなくなってきた。 理由がほしかった。会ってもしょうがないってどういうことか、もう少し私にわかるように説明してほしくて、東京にもどってからも私は毎晩電話をかけた。大学からまだ陽が高いう ちに帰宅し、暗くなるかならないうちからお酒を飲みだす。飲みながら考えることは決まっていた。いや、考えてはいなかった。考えるとは結論に向けて答えを導きだすこと、私はただ 「何で、どうして」をその人との十五歳からの思い出といっしょに洗濯機に放り込み、ぐるぐる回しているだけだった。 時計が十時を過ぎると私は居ても立ってもいられなくなる。当時まだテレフォンカードが普及していない時代、百円玉と十円玉をいっぱい作って握りしめて、近くの公衆電話ボックス へ行く。部屋を出る前には必ず、それまで飲んでいたものの三倍ぐらい濃くした水割りを一気に呷(あお)り、勢いをつけた。 電話の主が私だとわかると「ああ……」と困ったような声が漏れる。情けないけど、私は捨てられる女がよく言うセリフを台本通り言った。 「何か、私に悪いところがあったら言って。直すから。もう会わないなんて信じられない」 それでも何も言ってくれないその人に、次には、 「別に彼女じゃなくてもいい。妹みたいな存在でいいから、会わないなんて言わないでほしい」とも言ったと思う。さらには、 「もう、会わないっていうのはわかったから。わかったから私が納得がいくような理由を言って」と食い下がった。 それでもその人は答えてくれない。自分がみっともないことを言ったりしたりしているってことは、酔った頭でも十分分っている。でもなりふりなんか構っていられなかった。 気持ちがぷっつりと切れているのに電話の線は辛うじてつながっているものだから、無情な規則正しいリズムを刻んで、コインが落ちる音だけが電話ボックスで響く。相手は、私が手 持ちの小銭を使い果すまで、決して自分から切ることはしなかった。 しおれて部屋にもどる。もどるなり、部屋を出る時に飲んでいったのよりもっと濃いウイスキーを流し込む。悲しいのと自分が情けないのと、その人が自分の前からいなくなるという ことにこんなにも狼狽(うろた)えている自分に本当に呆れて、自分をどう扱っていいか途方にくれた。 幾晩そうやって電話をかけただろうか。その人は根くらべのように何も話さず付き合ってくれた。どうせもう会わないんだから、嘘でも本当でも私を納得させるようなことを言うこと など、その人だったらいくらでもできただろうに、何も言ってくれなかったのはどうしてだったのだろう。その人なりの優しさだったのか、さんざん振り回した私への報復だったのか。 相手が答えを出してくれないのだから自分で道をつくるしかなかった。お酒の力を借りながら何とか自分をこう言いくるめた。 〈私はあの人からたくさんのものをもらったじゃないか。理由はどうあれ、あの人がそれがいいと思ったことだったら、それで間違いないのだろうし、私は何も言わず受け入れるしか ないのだ。六年かかっても言えなかった言葉を今更引っ張り出したって、もう遅いんだよね〉 ただ今になって思うと、コトはもっと簡単な話であったかもしれない。私は高校生や田舎から出て行った大学生に成り立ての女の子としては、その人の眼鏡に叶う子だったのだろう。 結構何にでもむきになって頑張りをみせてまわりに媚びることも知らないような。都会に出るとそんな純な部分は少しずつ失われていくかもしれないが、替わりに人間としての幅を広げ ながら、したたかさみたいな処世術を身につけていく。それが大人になるということかもしれない。だけれど私は、自分の世界を広げることもできずに成長がとまってしまった。とりあ えずの居心地のいい場所ばかり探して、辛いことから逃げる策ばかり講じるようになる。「生きていく」ということと正面から向き合わない女の子になってしまった。いや、女の子だっ たら許してもらえるかもしれないが、歳も二十歳を越えようとしている女性が、それでは通用しない。 つまり、私に高校三年生の時に駅前の喫茶店で「単純に好きだよ」と言ってくれたように、その人は私のことが「単純に好きでなくなった」から「会わないようにしよう」と言っただ けなんだろう。嫌いになったわけでもないとしても、好きでもない相手とは、会うエネルギーも時間もないに違いない。それに、その人が私に気持ちを傾けていてくれた年月が長ければ 長いほど、成長がとまったというより、後向きになった池田を見ていたくなかったかもしれない。その人は私の口から、「あなた好みのおんなになるから別れないで」なんて台詞は、絶 対に聞きたくなかったんだろうなと今になって思う。 私の「心の二つの部屋論」は強(あなが)ち間違いではなかった。その場しのぎの詭弁でもなかった。ただ、あの時点ではもう一つの部屋の鍵がその人のもとに渡ることがあるというこ とは、考えてもみなかった。そして、私がもらってよと差し出した時、彼はいらないと背を向けて去っていった。振り返るといつでも傍にいてくれる人だと思って、信じて疑わなかった 私はなんて不遜な心の持ち主だったんだろう。いなくなってその存在の大きさに改めて気がつく。 その人が私の前からいなくなった。これは考えてもみないことだった。心に大きな穴があいた。その穴に待ってましたとばかりにはまり込んだのがお酒だった。 私はお酒にすがったのである。事実、その時は本当に自分にお酒があってよかったと思った。お酒がなくては長い夜が過ごせなかったから。ただ私にお酒があってよかったのか悪かっ たのか……。アルコール依存症の進行という点でいうと、たしかに拍車がかかった。 ただし、その人の名誉のために言っておくが、自分の飲み方を段階を追って遡ると、私はもう夏にはおかしな飲み方になっていた。つまりアルコール依存症ははじまっていたのである 。実際に私が医者にかかって診断されたのはそれから一年後の四年の夏である。今、アルコール依存症と向き合ってしばらく経つから、そんな判断を医者に任せずに自己診断する私であ るが、自分を含めて、その三年の夏の私の飲み方を異常とみた人は誰一人いなかっただろうと思う。そして、毎晩でも飲まないとソワソワするという心理的な依存の段階で、自分にした らの一大事が降り掛かってきた。それで量は一気に増えた。 夏休みの旅行からもどった頃には、毎晩数杯のおいしい水割りで済んでいたものが、自分の中でその人の件がなんとか整理できた頃には、私は寝るが寝るまでグラスを片時も離さず、 寝入るまで飲み続け、酔いの中でしか眠れないという飲み方が身についてしまい、量も毎晩ボトルに半分はあけるまでになっていた。 しかし私のような飲み方をしていた女子大生は他にもいたはずだ。病としてのアルコール依存症の発病当初の三年の夏、私はただの酒が強くて好きな女子大生だった。それが私以外の 彼女たちはそのまま「酒がイケル女性」でおいしいお酒を飲み続けることができて、私はアルコール依存症の道を驀進(ばくしん)した。その違いは何なのか。ぼんやりとは分かる気がす るが、きちんと言葉で伝えられるまでには自分の中でまだ考えが熟(こな)れていない。それさえ分かればアルコール依存症を予防する一助のそのまたお手伝いぐらいはできると思う。が 、今のところ私が体験的に言えるのは、アルコール依存症の予防は難しいということだけである。私だってその時点では、自分がアルコール依存症に足を踏み入れているなんて知る由も なかった。 失恋して、その心の傷を癒すために一時お酒に頼るというのは、世間では許されることのようである。「悲しい酒」や「ひとり酒」の歌詞が自分のことを唄ってくれているような錯覚 を起こすくらい、男と女・悲恋・別れに酒はついて回っている。心に傷を負った時「酒」という注射で症状を緩和している間に「時間」というよく効く薬が働いて、普通の人は心が癒さ れていくらしい。 ところがアルコール依存症者にとってその注射は、とんでもない副作用を起こすものであるようである。とてもよく効き、本当に素晴らしい特効薬だと思って服用していたらたしかに 心の傷は癒えたけれど、他の病が重くなっていた。あとで副作用が問題になって、製薬会社だけではなく医療や行政を巻き込んで大騒ぎになる何かの薬みたいだ。使用しているうちはま さか、こんなことになるとは誰も思っていない…… 時間のずれの悪戯がもう一つ。自分の中での整理がつきはじめ、「しょうがないんだよな」と思うしかしょうがない。そんなことが口癖になった頃だった。 また、あの筆跡の手紙を郵便受けに見つけた。 「何?」期待と不安、戸惑いながら開封した。 手紙の内容といえばまた遊びにおいで。今度はミニスカートなんか履いてくれば大歓迎だ、なんていう信じられない脳天気なものだった。 これはいったいどういうことなんだろう……私は狐につままれたような思いで数日過ごしたが、そのままではいられず、思い切って再び電話ボックスへ向った。できたら歌の文句じゃ ないが、「もう、会わない」が冗談であってほしいと思いながら。 久しぶりの私からの電話に困惑した様子、私は新たに届いた手紙の真意を問い正した。 「いったい、どういうつもりなの? 私のことからかっているの?」 「それ、消印見た?」 「えっ?」 急いで部屋に取って返し、よくよく見る。手紙本文は気楽に書いたものらしく日付は入っていなかったが、たしかに封筒の表書、左上に押された長野中央という丸印の日時は私が受け 取った日より、一ヵ月遡(さかのぼ)ったものだった。 今頃こんなものが届くなんて、残酷すぎる。いっそ届かないほうがどんなによかったか。一ヵ月もどこでどう迷っていたんだろう。地球を一周したってこんなに時間はかからなかった はずだ。本当にあの時は郵便局を恨んだ。遅配を知らせて詫びる一本の付箋が貼られていたら、私の心はあんなにも痛まなかった。料金が十円不足でも、郵便番号が一桁違っていてもそ のままにはしておかないだろうに。今、断酒会の関係でたくさんの郵便物を出したり受け取ったりしている。出したはずの郵送物が迷ってどこかにいってしまったことがないこともない 。だけど、一ヵ月も遅れて、それが律儀に届けられたなんて聞いたこともない。まあ、あの手紙がきちんと届けられていても結果的なことは変わってはいないだろう。それでもそのお陰 で私のあけたウイスキーのビンが数本増えたことはたしかである。 一年が経って、お酒の飲み方だけがいっそう異常になって、初めて精神病院に入院してしまった時、私は一度だけその人に院内から電話をした。いやな女だ。 「私、精神病院に入らなくちゃならなくなったの」とだけ言った。 私は二十一歳にして精神病院に入るという、この呪わしい運命を誰でもいいから分けて持って欲しかった。電話ではもちろんあなたに冷たくされたからとは言わなかったものの、そん なことを病院から電話するとは、自分の中にそれを言い訳にして酒に逃げた自分が出来上がっていたのだろう。 たしかに最初は、少しでも辛い長い夜を短くしようとお酒を飲んでいた。しかし、しだいに私は目的と手段が逆転してしまって、答えはとっくに出ているのに、自分の中でなかなか決 着がつかないことだけに執着して、それを酒の肴にして飲む癖がついてしまっていたのである。だからその一件がなくても私のアルコール依存症は確実に進行して、遅かれ早かれの問題 だけであることだけは明白だ。 アメシストの集いの体験談で、断酒をはじめたばかりの人、病院から退院したての人の体験談は、やはり自分がお酒を飲みだしたきっかけに終始することが多い。旦那の浮気であった り、嫁ぎ先の舅・姑との人間関係のもつれ、子どもの非行、商売の行き詰まり、更年期障害や妊娠などの女性特有の体の変調、果ては天変地異まで持ち出して、女性の場合探せばいろい ろあるらしい。実際、それが引き金になってお酒を飲みはじめたということを見極めることは、回復の入口に立った時のまずはじめの作業としては大事なことだと思う。 しかし、そこでとまっていては問題は解決しない。恨み辛みは飲むきっかけにはなってもお酒を断つ助けにはならないのだから。 回復の道を先に歩いている先輩に聞く。 「たしかに、飲み出したきっかけはあるでしょう。じゃあそれがなかったらアルコール依存症にならなくて済んだと思いますか」 十人に八人は言う「いや、時期はずれるだろうけど、他のことがきっかけで、結局はなったんじゃないかな」と。そこに回復に邪魔になる恨み辛みを乗り越えて、自分と向き合い、人 間的な回復、真の回復を目指している姿を見る気がする。 アルコール依存症に陥った外因は分かりやすい。でもそれだけではアルコール依存症になるはずがなく、その外因と気味がいいくらいはまってお酒に走った内因の存在はなかなか見え てこない。ただお酒をやめて、しらふでそれまでの自分と向き合い、自分探しの旅をはじめると、自分でも知らなかった自分が見えてくる。その出会いも新鮮である。 二十三歳、私は腰掛け程度の仕事をしていた。なんとか大学は卒業したが就職活動もろくにできずに、再入院を二度も繰り返したあと、祖母のコネである地元の団体に入れてもらった 。男性の補助的な仕事で、就業終了を報らせるチャイムの前に帰り支度をはじめるようなOLだった。職場は市の合同庁舎の中にあった。 何かの用があって総務課に行った。聞き覚えのある声、二年ぶりの再会に声を失う。向こうも驚いたようだったが、二メートルほど離れたところで会釈しただけだった。その人は支社 にいるらしい。 それから数ヵ月後、今度はエレベーターの中で二人っきりになった。三階から乗り合わせてそのエレベーターが一階に着くまでの数秒の長さ。 「飯田にいるの?」と声を掛けてくれた。 「通ってるんです」と答えたように思う。とにかく早くその場を立ち去りたかった。逃げ場のない箱の中、消えてなくなりたかった。 病院の中からあんな電話をしたことが恥ずかしかったし、仕事だって、当てがわれたことだけを手を抜けるだけ抜いてやっている自分が恥ずかしかったし、朝晩の通勤時間に電車の中 で缶ビールを飲んでいる自分も恥ずかしかった。その人の前で胸を張れる自分がどこにもいないことが恥ずかしかった。 一階に着くやいなや、何のために階下に降りてきたかも忘れてトイレに駆け込んだ。こんな「自分が嫌いな私」でその人の前に出たくなかった…… 「もう、会わないようにしよう」と言われてから二十年。エレベーターを逃げるようにして出てから十八年。 『描きかけの油彩画』が一つの形になった時、私はアルコール依存症者として生きる自分の人生に、もう一度、腹を括り直した。 断酒できている今とやめ続けていくこれから先の人生を大切にしていこうとはそれまでも思っていたが、これを書いて過去の自分が一つの形になった時、飲んでいた時もどこかで生き ることに必死になっている自分もいたはずだ、ということに気がついた。だから、他人から蔑(さげす)まれるそんなアル中時代の悔悟はしつつも、自分だけはその間の人生を大事にして あげようと思うようになった。 ここまで自分のアルコール依存症を公表して啓発の活動をしている私に、「もっと自分を大切にしたら」と言ってくれる人もいる。気持ちはありがたい。しかし私にとって自分を大切 にするということは、決して飲んできた過去に蓋をして、その時代がなかったものとして、普通の人生を装って生きることではない。それはまるごとの自分の人生を、これからの断酒の 啓発につなげることである。自分の飲んできた過去を体験として活かしてこそ、自分がこれからも生かされていく意味があると思う。 そんな思いから、地元の新聞社に県内女性酒害啓発活動の資料と『描きかけの油彩画』を持ち込んで、また紙面に余裕がある時に取り上げてくださいと気の長いお願いをしておいた。 そして忘れた頃に取材の申し出をもらった。 医療のきちんとしたお話も一緒に聞いてもらった方がいいと思い、暮れも押し迫って、医者の不養生なのか、風邪でダウン寸前の南風原先生を担ぎ出して取材を受けた。ところがすぐ に冬季オリンピックがはじまって、紙面は余裕どころの話ではなく、そのうち、取材を担当してくれた若い記者の方は本社へ転勤ということで、飯田からいなくなってしまった。 まあこんなもんかな、世の中なんて、でも南風原先生には悪いことしたなと半分あきらめかけていたところに、「文化部に配属になりました、改めて聞きたいことがあるので」とその 方からの電話が入り、再度取材を受けることになった。九州ブロック沖縄大会の前日のことである。 二十年前のその人が本社で活躍されているということは聞いていた。迷いながらも意を強くして、取材に来てくれた記者の方に、その人に渡してほしいと『描きかけの油彩画』をIから IIIまで三冊、託した。手紙も、と思ったがご無沙汰しておりましたもないもんだしなあ、など考えていたら結局適当な言葉がみつからないままで添えられなかった。そして、沖縄からは がきを出した。まず、突然私が現れてさぞ驚かれていることと思います、と断って、今回新聞で取り上げてもらえるお礼を言い、最後に「というわけで今は元気でやってます」と結んだ 。 沖縄からもどって二週間ほどして掲載になった。反響がかなりあって、日に何本かの電話が入った。お礼を言いたくて取材をしてくれた記者の方にまず電話をした。ついでに冊子を渡 した時のその人の様子を聞く。本当はこっちが主目的だったかもしれない。 「あっ、はいよ。ぐらいのものだった?」 「いいえ。なんだか、心配されてましたよ」 「本当……まあ心配してもらう時期は過ぎたと思うから。あとは応援してもらうだけだから」 電話をしよう……勇気は要った。でも私はしなのアメシストの啓発をしている池田倫子としてお礼を言うんだ。臆することはないじゃないか。ついでに、心配してくれているっていう んだから、もう心配ないです、って言えばいいんだ。 とはいうものの、受話器に左手を置いて深呼吸を何度かした。直通の電話ですぐにその人は出てくれた。 「飯田の池田ですけど」 「あっ……こ…んにちわ」 「このたびは……」とお礼につなげる。 「いやあ、読んだよ。『描きかけの油彩画』だっけ、三冊みんな。内容が内容だけにへたな返事も書けなくって」 そして言ってもらった。 「長野に来たら、連絡くださいよ。また会いたいし……」 また連絡させてもらいます、と言って受話器を置く。 「もう会わないようにしよう」と言われてから「また会いたい」と言ってもらえるまで二十年かかった。もちろんその「会う」という意味は同じものではないけれど、私はあの時ほど断 酒ができている今を嬉しく思ったことはなかった。 その人と電話で話ができて、そう言ってもらえた時、私は一つだけがどこかへいってしまって、どうしても仕上がらなかったジグソーパズルのその最後の一ピースがはまって完成した ような思いがした。 二十年という時の長さを簡単に言ってしまう自分の年齢を、改めてしみじみ思う。あんな出会いや別れがあった。そしてこんな再会がある。 その人が知らない二十年の間に私は見なくてもいい世界をいっぱい見てきた。きっとその人は『描きかけの油彩画』を読んでくれて、俺は君に世界を広げて幅広い見識を持てとは言っ たけれど、こんなところまでのぞいてこいとは言わなかったぞと思ったかもしれない。それでも私は生きてきた。そしてお酒を断つことができて、その姿だけはその人の前に出ても恥ず かしくない自分になれたと思っている。そんな私で会いたいと思った。もう私はあのエレベーターから逃げ出した私じゃない。お酒を断って生き抜くために、こんなに一所懸命になって いる私を見てほしい。 だから、長野に行く用事がありますから、もしできたら時間を作ってくださいと手紙を書いた。長野で午後一時から、社会福祉の通信教育の科目試験を受ける予定がある。午後二時、 その試験会場から近いホテルの二階の喫茶店がその人との待ち合わせの場所。しかし、今朝の女性からの電話で正午にその電話の主と会うことになった。 時計は十二時半を回った。女性はまだ来ない。眼鏡をかけている人を見かけると、声をかけたくなるが、どの人もはつらつとした表情をしていて、とてもお酒で悩んでいるようには見 えない。 しばらく店の前に立っていたが、じっくり待とうと私は店に入り、外の人の動きが観察できる場所の席で軽く昼食をとった。 試験は一時からだが、三十分前には会場に入るように注意書きがあった。どうしよう……、彼女は住所や電話番号はおろか、姓さえも私に告げようとはしなかった。唯一接点を持てる 可能性はここにしかない。もし私が席を立って、そのすぐあとにやってきたら彼女はどれだけがっかりするだろう。 「切羽詰まっているんです……」今朝の電話の奥のか弱い声が耳に残っている。人を試したり、悪戯や悪意のあるものでないことは応対した私が一番よく分っている。何か遅れるのには それなりの理由があるはずと思う。飲んでしまっているんだろうか。でも、相手を待たせているという思いは待っている人間の思いより数段辛いことを私は知っている。お酒に手が出て しまった。それが二杯三杯と重なってしまう、相手に悪いと思いながらもとうとう家を出られなくなる。結局大事な約束をすっぽかしてしまう。悔いながらも次の酒を飲もうとしている 自分。そんな私が過去にいた。その時の自分が蘇える。彼女が今、もしそんな最中にいるかもしれないと思ったら、自分のかつての姿がまだ会ってもいない彼女のイメージと重なって目 がうるうるしてきた。まったく日曜日のロッテリアで一人で涙目をハンカチで拭ってるなんて。 いよいよ試験に間に合いそうもなくなった。それでいいと思う。試験はまた次の機会にすればいい。私が私として何よりも優先させなければならないのは多分こういうことなんだろう 。待たされていることで少しも相手を責める気になれない。連絡がとれないことをもどかしくは思ったが。 それでも二十年ぶりのその人との時間までは使えなかった。喫茶店の入口近くのホテルのロビーで待った。最後まで迷ってやっぱり私は彼が来る前に、胸の銀のブローチをはずした。 今日の私はあの頃を懐かしんで会うのではないのだもの。 アメシストは紫水晶に変わってしまった。彼女がバッカスと出会ってしまって人間にもどれないように、私ももうあの頃のお酒の味も知らなかった女の子にはもどれない。不器用なく らい何事にも一所懸命だったあの頃。 それでも今、私は断酒にかけている姿だけは誇れる。だからあなたの前にも出られるのです。一人のアメシストに姿を変えて。 「まあ、いいや。元気なら」そう言ってレシートを持って先に立ったその人、私の前を歩く彼の背中が二十年の年月を告げていた。 --まあ、いいや。元気なら--その言葉を胸にあたためて、私は高速バスで飯田にもどった。 何だかまた泣けてくる。今日は情けないくらい涙腺がゆるい。でもその涙は温かかった。人生っていいな。生きてるって素敵だなって思う。 家に着くとすぐに電話が鳴った。 会えなかった彼女のか細い声が、また電話の奥から聞こえてきた。


 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~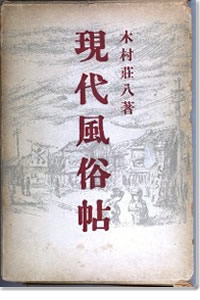 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白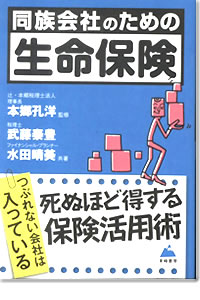 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内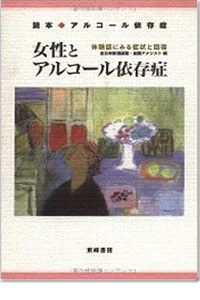 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート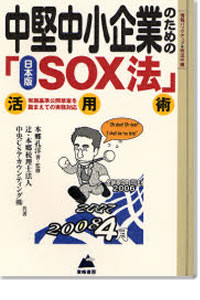 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日