| cover | ||
 |
描きかけの油絵 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
描きかけの油絵
こころの天秤
酒をこれ以上飲み続けるのなら家を出て行ってくれと父に申し渡され、酔った勢いでそれを受けた。そして、きっぱりと言われた。 「もうおまえのあと始末はたくさんだ。塾をたたんでから行ってくれよ」 二度とここに帰ってくることもないのだろうなと立ち寄った教室。外に掲げた看板の塾名にはガムテープが何本も貼られてあった。ここまでしなくてもいいのに……そう思ったが、脚 立に上ってわが子の名前の入った塾の看板の名称を消すことで、私への決別を示した父の覚悟の固さが痛いほど感じられた。 教室に一歩足を踏み入れると黒板に書かれたチョークの文字が私の胸を突き刺した。 --なんで、やめるんだ。ばかやろう--悲しい怒りは隣の村から通って来ていたゆうすけくんだろう。独特の右上がりの筆跡で彼とわかる。わりとチャラチャラしていた子だったの に、その数週間前、真剣な顔でどうしても行きたい高校があるんだと相談を受けたばかりだった。 隅っこにまとまって寄せ書きのように書いてあるグループ。大きく--やめないで--のまわりにそれぞれの名前を配した中学三年の仲良し五人組。イラストが得意なともみちゃんが みんなの似顔絵を描いて、それぞれの表情を泣き顔にしていた。そのうちの一人のあいちゃんは塾をはじめた時から通ってくれていた子で、出会った時小学校三年生だった彼女も、もう 足かけ七年のつき合いの中で、高校受験生に成長していた。 --みんなで勉強したいよ~--の延ばしたミミズが黒板の端まで届いていた。 ぐるっと教室を見渡す。鯉・鮫・鱈・鱒・鰊・鰯……教室の壁の高いところに貼ってある模造紙は、五十余りの魚偏の漢字。 その下にかかっているのはUFOキャッチャーの戦利品 の人形たち。ひょっこりひょうたん島の主役たちがほとんどそろっているのが自慢だったが、私の獲物は一つもない。みんな子どもたちが持ち寄ったものだ。 塾と教室に別れを言うために寄ったのに、思い出が多すぎて、子どもたちの気持ちが切なくて、それが私の足にからみついてその場から動けなくなった。半分酒が醒めかかった頭の中 で冷静になろうとしている私がいる。 〈本当にもう引き返せないのだろうか。あともどりできないのだろうか。「お酒、やめます。もう、飲みません。決してみんなに迷惑をかけませんから、どうか塾を続けさせてください 」、そう謝れば子どもたちと別れずに済む。あの子たちを裏切らずに済むかもしれない。自分が何をしようとしているのか、どれだけのものを捨てようとしているのかわかっているのか 〉 すると半分の酔いが私にささやく。 〈もう、ここまできたらぐずぐずしてたってしょうがないじゃないか。気が済むまで飲めばいい。なにを先生ぶってるんだ。あんたはただのアル中だ〉 〈ほんとにいいの?〉 〈いいもなにもないじゃないか。もう閉めるって貼紙もしてあるんだし。看板だってあの通り。子どもたちは慕ってくれたって、もうあんたの酒のことは親に発覚して、そんなアル中の ところに大事な子どもを勉強に通わせるものか。いままでの人生さんざん酒で取り潰してきたんだから、酒で塾を閉めるってのも、あんたらしくていいんじゃないの。いいとこ終ったっ てもんだ。それにもう、子どもたちの前で酒臭い息を詰めてしらふを装わなくてもいい。だいたいお前さんが人にものを教えようってこと自体が間違ってるんだ〉 〈だけどここまでくるのに、私なりに頑張ってきたんだ。中学三年生が十人もいるんだよ。もうすぐ夏休みだっていうのに、いまから塾を替わって違う塾にいったって馴染めない。あの 黒板のみんなの声を聞いてそれでも本当にこの塾、やめるつもり?〉 〈人のこと心配してる場合じゃないだろ。そんなこと言っている間にほらほら酒が切れてくる。子どもたちだって、今は先生行かないで、なんて名残を惜しんでくれていたって半年もす りゃあんたのことなんかみんな忘れてるよ。自分のしたいように生きたもん勝ちさ。なにがしたいって、酒が飲みたいんだろ。飲んでいられればそれでなにもいらないんだろ。もう、め んどくさいことはたくさんだ。さあ、門出の一杯、旅立ちの祝杯を挙げて、景気をつけようじゃないか〉 残っていた四割の酔いに完全に寄り切られて私は、ボストンバッグの底に忍ばせておいたウイスキーのビンをつかみ出してラッパ飲みした。門出の祝い酒にしてはちょっと淋しくて行 儀悪いがぐいっと一口、溶鉱炉から出たばかりの真っ赤な鉄の流れが食道から胃に入り込むのがわかる。切れかかっていた酒を迎えて、まるで干上がった大地が恵みの雨を吸収するかの ように胃壁は待望の液体を吸い込み、見る間にアルコールが動脈から毛細血管経由で細胞一つひとつに行き渡っていくのがわかる。この感覚を体が覚えてしまった限りには、私は地の果 てまでも「これ」を追い求めていくんだろうな…… アルコールが脳の細胞にまで届いたらしい。快いしびれが訪れる。口腔の粘膜がただれるほど口いっぱいにして飲み込んだストレートのウイスキー、その一口は塾を捨てて家を出る覚 悟を私にさせるのに十分な量だった。 黒板を一瞥(いちべつ)して私が塾を出ようとした時、教室の長机の上に置かれたものが目に入った。カレンダーの裏面にマジックで書かれた私へのメッセージだった。 「もし倫子がきたらこれを読んでください。お母ちゃんもお父ちゃんも何もしてやれなくてごめん。一生懸命していることが間違っているかもしれません。これしかできない。自分のこ とは自分で、自分の体に気をつけて下さい。それが一番の親孝行です。私は仕事にいきます。後は倫子の判断にまかせます。母より 倫子へ」 気の弱そうな字。ところどころが震えている。膝がガックリ折れて、その場にへたり込んだ。 〈なんで謝るの、私なんかに。この親不孝者って、親を殺す気かって、罵倒してなじってくれた方がどんなに気が楽か。悪いのは私なのは自分でもわかってる。お父ちゃんやお母ちゃん はいつも精一杯のことをしてくれたのもわかってる。 だけどもう、私の体は私の言うことなんか聞いてくれなくなっているんだ。お酒のいうままにしか動けない私になっちゃったんだよ。ごめん。どうにもならない〉 流れた一筋の涙は、唯一私に残っていた人間らしさだったかもしれない。謝りながら何度も何度も読み返して母の言葉を胸に納め、置いてあった場所に返した。破いたカレンダーは五 月、六月のもの、両親にとっては地獄の二ヵ月だったことだろう。私といえば酔いの異次元を彷徨(さまよ)っていて、開けたドアの向うにはそれまで住んでいた世界と違う空間が広がっ ている。半分、身を乗り出した私を一瞬母と子どもたちが呼び止めたが、私は引き返すことはなかった。母の最後の思いも私に憑(つ)く酒の呪縛を解くことはできなかった。 ただ、その声を振り切るには、もう一口のウイスキーが要った。しまい込んだボトルをもう一度引きずり出した。 こんな苦い酒、あっただろうか。 本当にお酒しか目に入らなかった。お酒がなければどうにもならなかった。 飲んでいる最中のアル中にとって、一本のワンカップは何物にも勝る価値を持つ。目の前に置かれている一本のワンカップを我慢したら、一週間後にたらふくおいしいお酒を飲ませて やるから、という交換条件を受け入れるアル中はいない。今飲む酒がほしいとなったら、自動販売機に使えない一万円札より、五百円玉の方が価値をもつ場合だってあり得る。 普通の常識が通用しない。まわりの者がなだめてすかして、時には天罰まで持ち出して脅かしながら人としての生きる道、倫理観を説いても「酒」の一文字は他のすべての価値観を凌 駕する。 それはそうだろう、「お酒をやめないなら会社を辞めてもらいます」と言われても、 「私たちかお酒か、どちらかを選んでください」と離婚届を突きつけられても、さらには「これ 以上飲んだら、命の保障はないですよ」と言われても、飲むのをやめようとしないのがアル中なのだから。 命に替えて酒を飲んできたとは決して比喩でもオーバーな表現でもない。少しずつ価値観を歪め、少しずつ酒のためにそれまで大事にしていたものを捨てていく。行き着くところは命 までも。 私も天秤の左の皿に命を乗せ、右の酒の重さと量ってその天秤の針の揺れを、酔った頭で虚ろな眼をして眺めていたことが何度もあった。アルコールによる人の死があっけないもので あるということを断酒会の中に入って嫌というほど見てきた。アルコールによる「死」は、ゆらゆら揺れる天秤の針が大きく揺れて、勢い余って振り切れただけのことであると思う。 しかし、最初から酒と命を秤にかけているわけでもない。初めのうち左の皿に乗せていたものは、職場での信用とか近所の面子(めんつ)とか家庭の和などそれなりのものだったはずだ が、次第により一層重いものを乗せていくようになる。家族、職、金、健康……いったいどれだけのものと酒の重さを比べてきただろう。ただ本人、しらふでその作業をやっているわけ ではないので、その天秤の目盛りが最初から狂っていることに気づいていない。 私が家を出る時、その上皿には山ほど大切にしていたものが乗っていた。両親との安住の生活、納得いく収入とやりがいのある仕事、慕ってくれる可愛い子どもたち、ふるさと…… けれどその時の私には一杯の酒がそれらよりも重かった。とうとうここまできてしまったけれど、私にだって「酒を非常識に飲むことが恥ずかしい」と感じ、羞恥心などというかわい いものを飲酒欲求と秤にかけている時代があったはず。 そういえば、こんなことがあった。消費税も導入されていなかった頃のこと、私はまだ二十歳代も前半だった。お酒やお金を両親に取り上げられても飲みたくて飲みたくて、なんとか どこかに小銭がないものかと、家中の引き出しという引き出しを捜して回った。あいにく小銭はみつからなかったが、そういえば……と板垣退助のことを思い出した。いつか価値がでる かもしれないと、記念切手と一緒にしまっておいた百円札がたしかあったはずだ。 十二枚出てきた。迷いもなくつかんで酒を買いに出た。ただ、困ったことに百円札では自動販売機が使えず、仕方なく対面販売の酒屋で買わなければならないことになる。今でも覚え ているが、私が棚からわしづかみにしてレジのおばさんまで持って行ったのは、ちょうど握っていた金額千二百円で買えるブラックニッカだった。おずおずとこれで売ってくれと財布に も納まっていない札の束を差し出した時のおばさんの怪訝そうな顔。 「あれ、困ったよう。百円札なんか、今どき持って来られても」 「大丈夫です。使えるはずですから」必死になって説明しても、百円札でウイスキーを求める若い女の話など信用してくれず、おばさんはその場で銀行に電話をした。 「お客さんが、百円札を持って買いにきたんですけど、使えるんですか。……あ、そうですか」 受話器を置いて「使えるっていう話だで」と言いながらヒゲの騎士を紙袋に入れた。そのおばさんの動作がわざと私を焦らしているかのようで憎らしかった。 〈使えるって、さっきから言ってるじゃないか〉私は紙袋をひったくるようにして店を出た。私の背中に浴びせられている冷ややかな視線を感じないわけではなかったが、それよりその ウイスキーを飲む物陰を探す方が先だった。 二十歳代前半よりそんな酒の求め方をしていた私であったが、年齢も次第に高くなると常軌を逸した飲酒を咎(とが)められ、「だったらどうするんだ」「どうするつもりなんだ」と場 面々々で酒と絡めての人生の選択を迫られることが多くなった。心の天秤は揺らいでいたが、いつも揺らぎながらも(続きは本書で)


 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~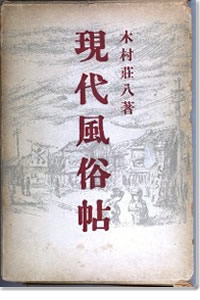 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白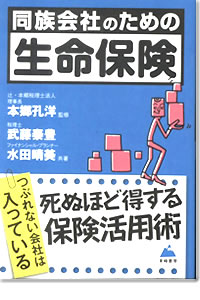 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内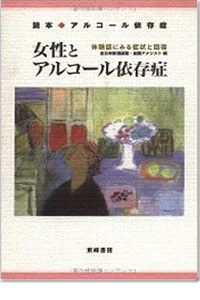 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート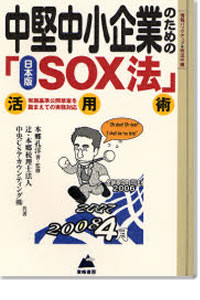 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日