| cover | ||
 |
描きかけの油絵 | |
| contents | お買い求めはコチラ |
描きかけの油絵
私の明倫学習塾
[明倫学習塾]--この名称に私は三つの思いを込めていた。まず、江戸時代の藩の学(まなび)舎(や)で「明倫」が多く使われてきたということ。萩の明倫館、名古屋の明倫堂など。そ して「倫」という字義の深さ。人偏と侖できちんと並んだ人間の間柄、ひいては「なかま」を表す。そしてなにより、自分が親からもらった名前の一文字…… 子どもたちと、塾という場で関わりをもつようになってからは久しい。大学を出て腰掛けの職に就いていた時もアルバイトでこの仕事はしていたし、振り返るとなんのかの言いながら ずっとこの畑にいたことになる。 離婚をして間なしの二十歳代半ばに、これからの自分の生活を考慮して、どうしたら口に糊をしていけるかと自分なりに考えてとった手段が、自営で塾を開くことだった。今のように 街の角を曲がればどこでも学習塾の看板が目に入る時代ではなく、けっこう生徒は集まった。 しかし二年間ほどはなんとかなっていたが、結局私は異常飲酒からあと片付けを父に押しつけて、自分は病院に逃げ込まざるを得ない事態を招いてしまった。 教室として借りていた一軒家のあと始末からはじまって生徒を他の塾に頼んだり、父兄の苦情の処理と、何から何まで両親に頼んで東奔西走してもらわなければならなかった。両親の 心労は大変なもので、自分でもこれはかなりの反省材料となり、その一件が尾を引いて、ときどき酒に手を出してはその酒が切れず精神病院の入退院を周期的に繰り返す身としては、「 責任を負う」ということに対して臆病になっていた。 三十歳だった。自宅の自室で近所や親戚の子の勉強を何人か教えていたが、ちょうど講師を募集している塾があり、条件が折り合えば週に何日か勤めてもいいと思って話を聞きに行っ た。ところがのぞいたその塾はオーナーが儲け話にのって、老後の収入の足しになればとはじめたチェーン店形式のもので、たいした理念もなくはじめたものだったらしく、学年の違う 生徒が一つ教室に押し込められ、塾が用意した教材を各々が自習しているばかりという実状だった。先生と呼ばれている短大生は子供たちから質問されると、おろおろしながらアンチョ コ片手に油汗をかいていた。一人の中学生が参観に行っていた私に密告するように囁いた。 「あの人、勉強の番をしとるだけでぜんぜん頼りにならんの」 子どもたちの不安そうな表情を放っておけなくなり、私は父母会を招集し、とりあえず勤める勤めないは棚上げして、このままでは子どもたちがかわいそうだから、みなさんの不満や 意見を本部に報告して改善される努力はしてみましょうと申し出た。 父兄の方々は、開塾の説明会での約束が履行されていない現況をあげつらい、怒りを爆発させた。そして、オーナーも思惑はずれで儲からず、父兄と本部の板挟みで近所付き合いも危 うくなっている事態に音(ね)を上げているようだった。もう投げ出したくなっている心境は手にとるように分った。 そんなところへの私の出現だ。だから不満を吸い上げるために招集した父母会では、「池田さんが塾をはじめてくればいいんだがなあ」という提議が一人のお父さんからされ、閉会の 頃には「それが一番の解決策だし、はじめてもらわないとこちらも困る」にまで話が進んでしまった。 思わぬ展開に戸惑いながら、三日間の猶予をもらって家族とも相談の上で答えを出させてもらうことにした。 家にもどって両親に事の顛末を説明し、どうしたもんかと相談を持ち掛けた。母は反対した。お酒は抗酒剤を服用することでその時はなんとかとまっている数ヵ月だったが、いつ何時 飲みだすかわからない私だったから。前科を引き合いに出して、責任のある仕事には就かない方がいいという意見である。 「責任」という言葉を持ち出されるとたしかに弱いが、私だってこのままの人生に甘んじていたくないという思いは強かった。だから確たる自信こそなかったが、一つのチャンスの到来 と捉えたい。やってみたいと両親に言ってみた。 塾が乱立する今、鐘や太鼓で募ってもなかなか集まらない生徒がまとまって私に勉強を習いたいと言ってくれている。場所は前のオーナーが家賃を払えばそのまま使ってくれていいと 言っている。これをみすみす見逃す手はない。それにここで塾を構えて子どもたちと接することで、懸けるものができればお酒のことも自然と解決していくかもしれない、酒を断つとい う強い意志はその時の私にはなかったが、塾が自分の抱えるアルコールの問題解決の糸口になり、人生が「なんとかなる」かもしれないと本気で思ったのである。 父は私の考えに賛同してくれた。父としては身についてはおらずとも、やはり自分たちが汗水流しての労を尽くして出した娘の大学卒という肩書きが、少しでも活かされる職なり行く 末は魅力に感じたことだろう。それに何より、やはり父も責任ある立場にあればやりがいもでき、それが生きがいにもつながって、お酒から遠退いた生活ができるようになるかもしれな いと考えたのである。 不安な材料を抱えながらも明倫丸は出帆した。それまでの近所付き合い、親戚付き合いで教えていた子も含めると、急に二十名を超える生徒を抱え込み、寝ても起きても考えるのは塾 とそこに通う子どもたちのこと。一所懸命はたしかだったから、親身になって勉強をみてくれる先生ということで、評判は上々で、宣伝もしないのに子どもらが友達を連れてきて生徒の 数は見る間に膨れあがった。 入塾の希望者が来るとまず、体験的に授業を受けてもらい、その後親御さんを交えて面談をし、学習していく姿勢を確認した。 「学校は生徒が先生を選べないし、先生も生徒を選べない。だから生徒が教わりたくないとか先生側がこのまま教えていても成績が上がりそうもないと思っていても、お互いが我慢しな けりゃならない。馬が合わなくてもね。だけど塾はそうじゃない。君はたくさんある塾の中からこの塾を選んでくれたけれど、逆にいえば塾側にも生徒を選ぶ権利はあるわけだ。塾は月 謝というはっきりしたものを真ん中に挟んで、お互いが納得できたときだけ関係が成り立つんだよ。学力の向上という形のないものに対してお家の人にお金を払ってもらうんだから、私 も自信をもって月謝袋を渡したい。毎月、月謝袋に入れてもらうお母さんがパートで働いた尊いお金を、死に金にするようなことをウチの塾じゃしたくない。私も一所懸命やるから君も あとで後悔しないために、せめて卒業までの間、精一杯やってみよう。その姿勢で通ってくれるなら、一緒に勉強していこう」そんな話をした。 私がそんな偉そうなことの言えるだけの人間かといわれると二の句が継げないが、ただ子どもたちのことは大事でかわいかったし純粋に大好きだった。実際、そんな私の大言にもかか わらず通ってきてくれていた子たちは、本当に素直ないい子ばかりだった。急におしゃれになったり、男女交際がどうのとか、勉強以外のことにうつつを抜かしていて困るなどと、親御 さんから菓子折り片手の相談を受けることもままあったが。 今、巷では中学生の「切れた」上での行動が刑事事件、殺人事件にまで及んでいることを憂える報道が続いている。背景のナイフの所持というニュース性も手伝って、連日ワイドショ ーでも取り上げられ、現代少年像を学者・教育者・医者・カウンセラーは横文字交じりで難しく話している。しかし、私は世の中が騒ぐほど少年少女自体が危機的な状況にあるとは、少 なくとも関わってきた子どもたちからは感じることはできなかった。物が豊か過ぎること、情報が流す方の論理でやたらに社会に流出するために、取捨選択の能力がまだ備わっていない 子どもたちが、その害毒を被ることは危惧しなければならないだろうが。 子どもが社会を映す鏡であるとはよくいわれることである。だからまず、子どもがどうのを論ずるより先に、世の大人や社会自体の歪みやひずみを正すべきだろう。それらのことを脇 に押しやっておいて子どものナイフや覚醒剤の所持、援助交際などをとやかく言っても何の解決にもならない。 子どもそのものは本質的には今も昔もあまり変わっていないと私は思うし、思いたい。ただし、彼らは「立場」でしか話ができない大人を嫌う。しかし、自分たちに媚びてきちんとし た態度がとれない大人をもっと馬鹿にする。ここのところだけでも踏まえるといい付き合いができるのではないかと思うが。 私は怒るべき時は本気になって青筋を立てて怒った。手だって出した。だからといってそれでやめていく子はいなかった。遊ぶ時は一緒になって真剣になって遊んだ。 期末テストが済んだあとは、大トランプ大会を敢行してみんなで熱くなった。家ではファミコンしかしないような子がちゃんとみんなでルールを作り、それを守り、協定を結んだりし ながら五十三枚のカードに自分の運と知恵を託して必死になる。停電になったら使えない機器に頼らずとも、二時間でも三時間でも仲間で興じることができるのである。たぶん両親を含 めた世の大人で、そんなキラキラした中学生の表情を見たことがある人は少ないと思う。 子どもたちの前で私も自分を繕うことはしなかった。いいことかどうかはわからないが、上司や教育委員会という、うるさいことを言う機関がないので、世の中が「よし」としている ことでも私が「なんか変」と思ったことは、自分なりの捉え方を伝えたし、自分が付き合っている彼氏とうまくいっている時は(七年の間には私にだってそんな時期があっても不思議じ ゃない)嬉しくなって黙っておられず聞いてもらった。別れた時もこんな事情の展開があってなどと事後報告をした。もちろん話すクラスと生徒は選んだが。春休みの一泊バス旅行も毎 年のお楽しみ行事だった。 スタートをさせて半年経ち、先の目鼻がついたところで自宅の敷地内に十畳のスペースが二部屋の教室を建てた。一部屋は教室に、もう一部屋はいつ勉強にきてくれてもいいようにと 自習室に当てた。器を建てるために銀行からのいくばくかの借金もしたが、それも半年で返した。借金の返済は励みだった。 少人数制が大原則だったので一番多いクラスでも六名を超えないように心がけ、習熟度の違いで手をかけなければならない子には月謝に拘らずマンツーマンで指導をしたり、場合によ っては授業の回転効率も考えず、二名のクラスも作ったりした。という臨み方で勢い人数が増えればクラスの数、授業の数もそれに比例して増え、みる間に自分の時間が削られていった 。初めの一、二年は年間を通しても四日間しか休まなかったし、実際そんなぎりぎりの体制に子どもたちも生活を融通しながらよくついてきてくれた。 年末年始の休業中も、よその塾が大晦日と元旦を休みにするという情報が入ると、それじゃウチは大晦日もやろうと受験生にハッパをかけた。だから収入はそれなりについてくる。塾 を開いて子どもたちを預かるか預からないかという決断に迫られて、受けますというからには、私も私なりの腹の括り方をした。「四十歳までは結婚しないつもりで頑張りますから、安 心してお子さんを預けてください」と言い放った。 それまでどこか頭の隅に結婚の二文字があった。さあ、といって相手がいるわけではなかったが、自分のアルコール依存症であることの重大さや深刻さを過小に考えていた私や両親は 、「誰か適当な人がいたら」とまわりの面倒見のいい人に声をかけていた。相手は再婚がいいけど子どもはない方がいいとか、養子になってくれなくてもいいから、できたら両親と一緒 に暮らしてくれれば申し分ないとか、都合のいいことを言って、誰か網にかかってくれないかなどと思っていたのはたしかである。両親も自分たちもいつまでも若くないから、誰かに娘 のことを任せたいと思っていたのだろう。酒がとまらない娘を結婚させることは心配だが、一人にしておくことのほうがもっと不安だったのかもしれない。 しかし、子どもたちを引き受けて塾を開くと決めた時、はっきりとこの二文字を頭の中から期限を切って消去することにした。女の先生に子どもを任せても、いつ結婚されてほっぽり 出されるかという不安材料が親御さんたちにあることは十分承知していたから、そう明言することで私はこの塾に懸ける意気込みをアピールし、同時に覚悟として自分にそう申し渡した のである。当時三十歳、四十歳までの十年が何をもって出した線だったかは定かではないが。 まあ、結局「四十歳までは結婚しませんので」ではなく、「できませんでしたので」ということで今に至っている。そんなどうでもいい口約束はしっかり守ったのに、一番大事な約束 を破って私は七年目にして子供たちを放り出してしまった。 たしかに初めの頃はお酒のことを考える余裕も時間もなかったことは事実だった。全てが順調に回りはじめ、塾をはじめたことは正解だったと家族はもちろん、周囲の者はみな思った だろう。一番手応えがあったのは他でもない、私自身だった。 しかし、その時自分の手で「造っている」という手応えのあった自分の城も砂上の楼閣。今思うと、私が塾をはじめたばかりの数ヵ月酒がとまっていたのは、アルコホリックがワーカ ホリックに一時すり代わっていただけのことのような気がする。根本的には何も変わっていなかった。かえって自分が一人前に社会で通用する人間になったようなとんでもない勘違いが 身についてしまったことは、人間性の回復という面からすると後退だったかもしれない。 初めは塾を回していくことだけで精一杯だったのが、よく言うと余裕がでてきたということであろうが、二年、三年と経つと少しは手の抜き方も要領も分ってくる。知らなかったお金 の使い方も覚えた。いつ飲むかわからないからと車を持つことは許してもらっていなかったが、「車一台、子守をすることを考えたら安いものだ」と着物に現(うつつ)を抜かしていた時 期もあるし、習いはじめたお茶の道具で贋作をつかまされて、自分の眼力のなさを嘆いたこともある。貴金属を衝動買いしても両親は、酒に気をとられるよりおしゃれに気が回るくらい だからいいことだと笑って見ていて、私の賄いに口を挟むことはなかった。 父が六時前に出勤し、汗まみれになって煎餅を焼く十二時間労働で得るより多いお金を私は夕食後の一稼ぎで手にすることを覚えてしまい、「働く」ということのもつ本当の尊さを身 を以て知ろうとはしなかった。お金は得ていたが、一方で人として大事なものを失っていった。 一緒に暮らして、ときどき暴れだす私のアル中の虫の面倒もみてくれる両親がいてくれなければ、七年と言わず、もっと早い段階で塾を閉めなければならなかったことは必至だったろ うに、一人で塾をやっているような不遜な考え方になっていった。そして、私がアルコールの代わりになってくれたらという塾は、一時期その代用品としての役目は果たしてはくれたが 、あくまでも代用品にすぎなかった。 たしかに最初の一年はなんとかなったものの、翌年にはさっそく精神病院の世話になり、だんだん入院と入院の間隔が狭くなっていった。何度挑戦しても、上手(うま)く飲めず、入院 を余儀なくされる。 初めのころは寝酒で一週間ほどはなんとか味のわかる酒が飲めているのだが、ある時を期してタガがはずれたように連続飲酒となる。その味がわかる期間もどんどん短くなっていった 。浮腫んだ顔、赤い目、そして挙動不審、問い詰められて白(しら)を切ることができなくなると再飲酒がはじまってしまったことを白状せざるを得ない。 それでも初めは即日入院ということはなかった。なんとか入院をせずにこの場を乗り切ることができれば、大難を小難で済ますことができると並々ならぬ両親の努力が払われた。まず 二十四時間の監視がはじまる。二、三日は部屋で一人で寝ることも許されず、親子三人が毛布にくるまって茶の間で雑魚寝した。私の行動は寝ている間も一挙手一投足がチェックされ、 尿意を感じて起きると、まるでセンサーが働くように両親もむくっと起き上がる。「どうした……」「……おしっこ」その後トイレまでついてくる。 しかし、親も私に飲ませまいとするなら、なんとか飲んでやろうとする私も必死で、あらゆる知恵と経験を総動員させて、そんな状況からも酒を手に入れて飲み続ける。そしていよい よ切れなくなると両脇を抱えられての入院、診察室などは素通りして、直接病棟へ向う。暇を持て余している長期入院のお馴染みさんは、私が入って鍵がかかると寄ってくる。 「あれぇ、倫子さん、どうしちゃったの」 吐き捨てるように言う。 「またお酒を飲んだの!」 あとは布団を頭から被って一刻も早く離脱症状が退いていくのを願い、大波のように押し寄せてくる後悔との格闘となる。 ただ、何とか塾は続けさせてやろうという主治医の温情から、親が責任をもって送り迎えをするという条件で、時期を見計らって病院から塾への出勤は許された。 授業を終えて子どもたちを教室から送り出すと、物陰から父がのそっと現れる。 「看護婦さんに迷惑がかかるから早く病院にもどる支度しろよ」 時間を繰り上げて授業を終えても病院にもどると他の患者さんたちはもう、眠前薬がしっかり効いて深い眠りの中だった。懲りずに何度同じことを繰り返したことだろう。 アルコール依存症は進行性の病気である。一時飲まない時期があっても、とまっていても、病気の症状が好転するわけではなく、断酒しない限りは必ず一歩、一歩とXdayに近づい ていく。 とまっていればいたで、一旦飲み出すとそのとまっていた期間を取りもどすかのように一気に大量を呷(あお)り、泥のように正体がなくなる飲み方になるまで時間が要らなくなる。 断酒会に入ってからもよく耳にするのが、断酒していく上での一つの手立てとして、生活の中で酒に替わるものを見付けることが必要であるという考え方。別の言葉で、「アルコール によって空いた心の穴を塞ぐ蓋を見付ける」と表現した人もいた。しかし、私は自分の経験からもこれはある面では危険を孕(はら)んでいると思う。 「断酒」することは大切な回復への原点ではあるが、「断酒の継続」にはそれ以上の重い意味がある。禁酒と断酒の意味合いの違いを明らかにしておく上でもこれを踏まえなければなら ない。つまり、アルコール依存症が一生の病(障害)であるからこそ、断酒を生涯の問題と捉えるべきであるし、そういう捉え方が自分自身の中でできた時に初めて、断酒が人間性の回 復=真の回復にまでかかわるのだとも思うのである。 さらに言うと「アルコールの代用品」や「アルコールによって空いた心の穴を塞ぐ蓋」を見つけるという考え方は、断酒のきっかけとしては分かりやすく、とっつきやすいが、代用品 が役不足になったら、あるいは蓋が外れたら、再び酒に手を出す可能性が高いことも同時に示唆している。体で覚えた断酒なら、そう簡単には酒に手は出ないかもしれないが、それでも そこで生きていく方向や目的を見失い、心に迷いが生じるかもしれない。 だから、「いままで飲むために当てていたが、酒をやめてぽっかり空いてしまった時間」を例会出席の時間に替えたり、断酒の仲間と一緒に過ごして、その時間帯に否応(いやおう)な く襲ってくる飲酒欲求を封じ込めるという方策は有効であると思うが、それを拡大解釈して他に意識を向けることで酒への捉われから逃げようとするのは、根本的な解決にはならないと 思う。 とりあえず酒がとまるんだったら何でもいい、と空いた心の蓋や酒の代用品を俗に言われるパチンコ・睡眠薬・買物・セックス等などに求めたら、アルコールはとまっていても問題は 解決しないどころか、広義の依存症としての病は単純でなくなり、対象を替えて依存を繰り返すことになると治療も厄介になるだろう。 とはいうもの、断酒の道につかせてもらって、曲りなりにも酒がとまっている今だからもっともらしくそんなことも言える私であるが、塾をはじめた時は、これでうまくすると酒がと まるかもしれないと真剣になって思ったし、塾がアルコールに替わるものになり得ると期待し、託してみようと思ったことも事実である。しかし世間の誰もが納得して、それはいいこと だと見做(みな)してくれるような私にとっての「塾と子どもたちに懸けること」さえも、アルコール依存症を継続的に治療し、癒してくれることにはならなかった。 では、塾を代用品としてあるいは心の蓋としてお酒が数ヵ月とまっていた時と、断酒が継続できている今と何が違うのだろうか。 たしかに塾が軌道に乗って収入も安定し、旅行に行きたい、着物が買いたい、指輪が欲しいとなったらそこそこ、そんな大それたものでない限りには手に入るようになった。それに名 乗る時「学習塾を自分でやっています」と言えば、私の抱えるアルコールの問題を知らない人は私をいっぱしの社会人と見てくれる人がほとんどで、一応の社会的な対面は保てた。加え て非婚の女性は珍しくない今のご時世だから、そのことはあまりとやかく言われることもなく、生活していく場面々々で、とりあえず今が喜べる条件はそろった。 しかし、よく考えてみるとその喜びというものは、酒がやめていられること自体の喜びではなく、酒をやめていることに付随している物や事象に気をよくしているだけのものであり、 自分の物や金銭や社会的対面を保ちたいという欲を満足してくれるもの、それに通じる喜びに過ぎなかった。お酒がとりあえずとまっているからこそ手にできている束の間のものなのに 、私は「こそ」の部分に目を向けようとしなかった。 欲は放っておけば際限なく広がる。すると次第に代用品は代用品としての用を為さなくなり、蓋は穴を覆いきれなくなっていつかは外れる。だから一時は順風満帆の航海をしていたよ うな明倫丸もアルコールの高波がきたら、いとも簡単に転覆してしまった。 そして今。今の私を支えてくれているのは「断酒の歓び」であって、それ以外の何ものでもないとはっきり言える。それとほとんど重なっているのが仲間との絆である。断酒の歓びを 堪能するために、時として物やお金や時間に窮屈な思いをすることもあるが、それを補って余りある「歓び」を断酒自体の中に見出すことができた今は、そんなことにあまり頓着しなく なった。 ホントはこれが幸か不幸かはわからない。世間のモノサシからしたら「そこまでしなければお酒がやめられず、まともな生活が送れないなんて気の毒に」などと思われているかもしれ ない。しかし、そうだとしても、私は今の姿勢や方向を口さがない世間に合わせて変えるつもりもないから、こんな自分の状況なり境遇を「よし」とし、迷いがない自分でいられるだけ でも幸せなのだろう、そう思うことにしている。 以前にアメシストの集いで「お酒をやめているのに、ちっとも生活が楽にならない」ということが話題の中心になった。テーマがあったわけでもないのだが、自然とその方向に話がす すんでいった。みんな置かれている立場は違うけれど、人間関係、金銭問題、社会の偏見……あらゆるところで苦しい場面に直面しているようだった。果ては「せっかくお酒をやめてい るのに……」と禁句の「のに……」が口をついて出て、何だかその場の雰囲気が暗くなっていった。 しかしその場に居合わせた私が尊敬する、関西のある会の会長さんの一言でみんなの心の向きが変わったのである。 「楽になろうと思いなさんな。断酒なん、楽なはずないんやから。だけど楽やないからやめる甲斐もあるんやで。誰でもできる楽なことやったら歓びなんておまへんがな。みんな一人ひ とり、いろんな大変な事情を抱えながら、そんな中でも一滴の酒に手を出さへんでこうして一日断酒を重ねて、今日も生き長らえることができる……かけそば一杯のうまさを泣きもって 食える、人と人の絆が嬉しい……これが“断酒の歓び”や」 これだと思った。まさしくこれが断酒継続の原点であると確信した。断酒会の中でこの断酒の原点の歓びを体感できている今だからこそ、こうやって自分の過去の打ち明け話を体験談 と称して話せる私がいる。拙(つたな)いのは百も承知の断酒理論だけれど、これは私が体で感じ、体験したことに裏打ちされた借り物でない自分の言葉だから聞いてもらいたい。そして 今、掌中にある「断酒の歓び」を伝えたい。 明倫学習塾の看板は一度は父の手でガムテープが貼られて消された。あれから五年の年月が経ち、今再び細々とながら毎日教室に灯を点して子どもたちを待つことができている。流行( はや)らせようと躍起になったのも遠い話。今はできるだけ長く子どもたちとかかわっていきたいと思っている。 解くのに一生かかる、いや一生かけても解けないかもしれないアルコール依存症という宿題を神様から出された私にとっては、たかが学校の成績と言いたいが、されど成績。 それでも、もう決して大切なものをアルコールの代用品になどすまい。塾とそこに通ってくれる子どもたちは別の宝物としよう。 不思議なことに人が手を加えないのに、看板のガムテープは剥がれ、気が付いたら少しずつきれいになっていた。飯田にもどったばかりの一時期はテープの剥げ跡が無残だった看板も 、五年間の太陽光線と雨と風と雪のお蔭で洗われていくように年々蘇ってきている。見過ごすほどの私の塾の看板は、あと三箇所の剥げ跡が落ちれば完全に復元する。 私はそれほどの回復力はないし六年、七年と言わず、生涯かけて真の回復を目指さなくてはならないのだろうが、それでもお酒さえ断ち続けていれば必ず時間が助けてくれて癒えてい くこともあるんだ、と、その「明倫学習塾」の看板を見るたびに酒を断ち続ける覚悟と生きる勇気が湧いてくる。 ●アメシスト 〈アメシスト〉 ギリシャ神話に登場する女性です。酒の神バッカスが道で最初出会った人間をお供の虎の餌にしようと決めて道を歩いていると、ちょうどその一人と一匹の前に出くわしたのが神殿に 参拝に行く途中のアメシストでした。「どうか、私を食べないで」彼女が命乞いをして神に祈ると、彼女の体は白い石になってしまいました。哀れに思ったバッカスは手に持っていた葡 萄酒を石に注ぎました。するとその石は見る間に紫に輝く石-アメシスト-に変わりました。それに由来して紫水晶(アメシスト)には泥酔から守るという石のことばがあります。 その人との再会で私が最後まで拘(こだわ)ったのは、銀のブローチのことだった。十八歳の時にもらったもので、止め金のところが壊れて以来、ずっと私の宝石箱の隅っこに追いやら れていた。 だいぶ前になるが、今は小学校の四年生になった姪に宝石箱の整理をして、いらないものを全部やったことがある。片っぽなくしたイヤリングだとか、アクセサリーに興味を持った二 十歳前後の頃、ただ数のうちと求めたネックレスだとか、多分身につける機会はないだろうという観光地土産のブローチだとか。姪は光っていさえすれば喜んで私があてがった鏡のつい た子供用の宝石箱に、それらを次々に大事そうにしまい込んだ。私の妹は「お姉ちゃん、可愛い姪をあんまり光り物が好きな女の子にしないでよ」と言って笑っていた。 私は奥から出てきた銀のブローチを手にしてしばらく眺めた。細かな銀の細工が施してあったが、それが銀独特の錆がきているものだから、何の金属かもわからないくらいに変色して いた。少しとまどったが、「これもね」と姪の宝石箱に入れた。 やるといっても“燻し銀”の言葉も知らない姪は喜ぶ風もなく、他のものと一緒に並べていた。母の立場として子どものもらい物の点検をする妹。目ざとく銀のブローチに目をつける 。 「これ、銀じゃない。それもこんな手の込んだ……いいの?」 「うん。軽くて重宝してたんだけど、止め金のところが壊れちゃってもう使えないし、修理に出すとしても、けっこう直し賃も取られるでしょ」 「これ、たしかお姉ちゃんが前に付き合ってた人からもらったもんじゃなかったっけ。とっておいた方がいいんじゃないの……」 「……そうかなあ……そうしようか」 で、そのブローチは姪のおもちゃにならずに、またその後も私の宝石箱で生き長らえていた。 二十年ぶりに会うことになって、そのブローチのことを思い出した。宝石箱の隅から、いっそう変色の進んだそれを取り出して、ベージュのパンツスーツの下に着る黒のタンクトップ の胸元にあしらってみた。付けていっても、これだけ色が変わっていたら、あの時のものとは分ってくれないだろな……長野行き高速バスの時刻も迫っていたが、私はやおらそれを磨き にかかった。しばらくの間、ジュエリー用洗浄液に浸けておいたがいっこうにきれいにならない。仕方がない、あとは家中の洗浄効果のありそうなものを総動員させた。歯磨き、台所用 クレンザー、研磨材入りのタワシ。歯ブラシを一本ダメにして必死に磨いていると、それでもだんだんそのブローチは銀の輝きを取りもどしてきた。 キッチンの流しで格闘していると一本の電話が入った。台拭で手を拭いながら、〈この忙しい時に……〉 「もしもし」 「あのう、二週間程前の新聞で……」この声の力のなさ、女性の酒害相談である。 「新聞で拝見したんですけど、あの、出てらした方ですか?」 「はい、そうです。お電話下さって本当にありがとう」 「あの、秘密は守ってくださいますか」 「もちろんです。随分とお困りですか」 「……もう、切羽詰まってるんです」半分、涙声になっていた。 「どちらからお掛けですか。あの、私、用事があって、これから長野市に行くんです。もしよかったらお会いしませんか。飯田発八時四十五分の高速バスに乗るんですけど、お住まいは 長野市から遠いんですか?」 「いいえ、飯田まではとても行けませんけど、長野でしたら出られます」 「じゃあ、どこか私にもわかる場所を指定してくださいな」 正午、長野駅からステーションビルに連絡する改札口を出たロッテリアが待ち合わせ場所となった。 「すみませんけど、上のお名前だけでも聞かせていただけませんか」 「えっ……」 「わかりました。私、ベージュのスーツ着て、黒のバッグ持ってます。背は割りと高いから、見つけてくださいね」 「はい。私は眼鏡かけてます」 なんだか今日は思わぬ展開になりそうだ。 時計を気にしながら最後の身仕度を終えて、私はそのブローチを胸に家を出た。止め金の壊れたのはそのままだったが、針金を曲げて細工のくぼみに差し込むことでなんとか胸にくっ ついていた。 その銀のブローチの贈り主との出会いは二十六年前にも遡る。当時の私の住まいは伊那。父の商売や何やらの都合で、私は幼い頃より飯田と伊那で何度も住まいを移していた。高校時 代を過ごした伊那は、信州の南の端っこの飯田から距離にして五十キロほど伊那谷を北上する。 自分が周囲の反対を押し切ってまでして、望んで入った高校だったのに、私は入学してまもなく、とんでもないところに来てしまったと後悔した。一クラス四十七人中、女生徒は三人 。自分の居場所がみつからない。 二時間目を過ぎた頃から教室のあっちこっちで早弁が広げられて、授業がはじまっても教室にはおかずのにおいが充満している。同じ中学の出身者もクラスにはおらず、私以外の女生 徒も、皆その人なりの確固たる世界を持っている風で「ねえねえ」と擦り寄っていくこともできなかったし、もとより当時の私は相手が同性であれ異性であれそういう人懐っこさはなか った。 教室にいるうちはまだよかったが、教室移動で廊下を歩いていて、前から三年生の集団など来ようものなら、私は狭い道で大型ダンプを避ける児童のように、壁に背をぴったり付け、 息を詰めてその一軍団が通り過ぎるのを待った。 男子ばかりの教室で休み時間も手持ち無沙汰、友達もおらず、居たたまれない毎日が(続きは本書で)


 古典語典
古典語典 シニアビジネスは男がつくる
シニアビジネスは男がつくる 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負! 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査 西洋古典語典
西洋古典語典 東京の季節
東京の季節 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~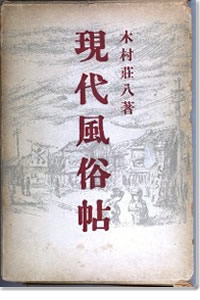 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白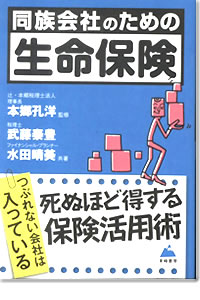 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代 江戸の物売
江戸の物売 江戸の看板
江戸の看板 信州の石仏
信州の石仏 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内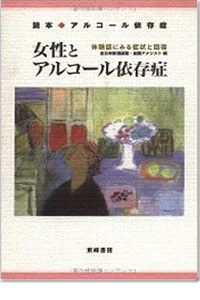 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復 版画の歴史
版画の歴史 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス いま、日本にある危機
いま、日本にある危機 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか? 長生きの国を行く
長生きの国を行く 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい 経営ノート
経営ノート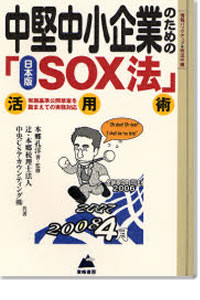 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55 バンクーバー朝日
バンクーバー朝日